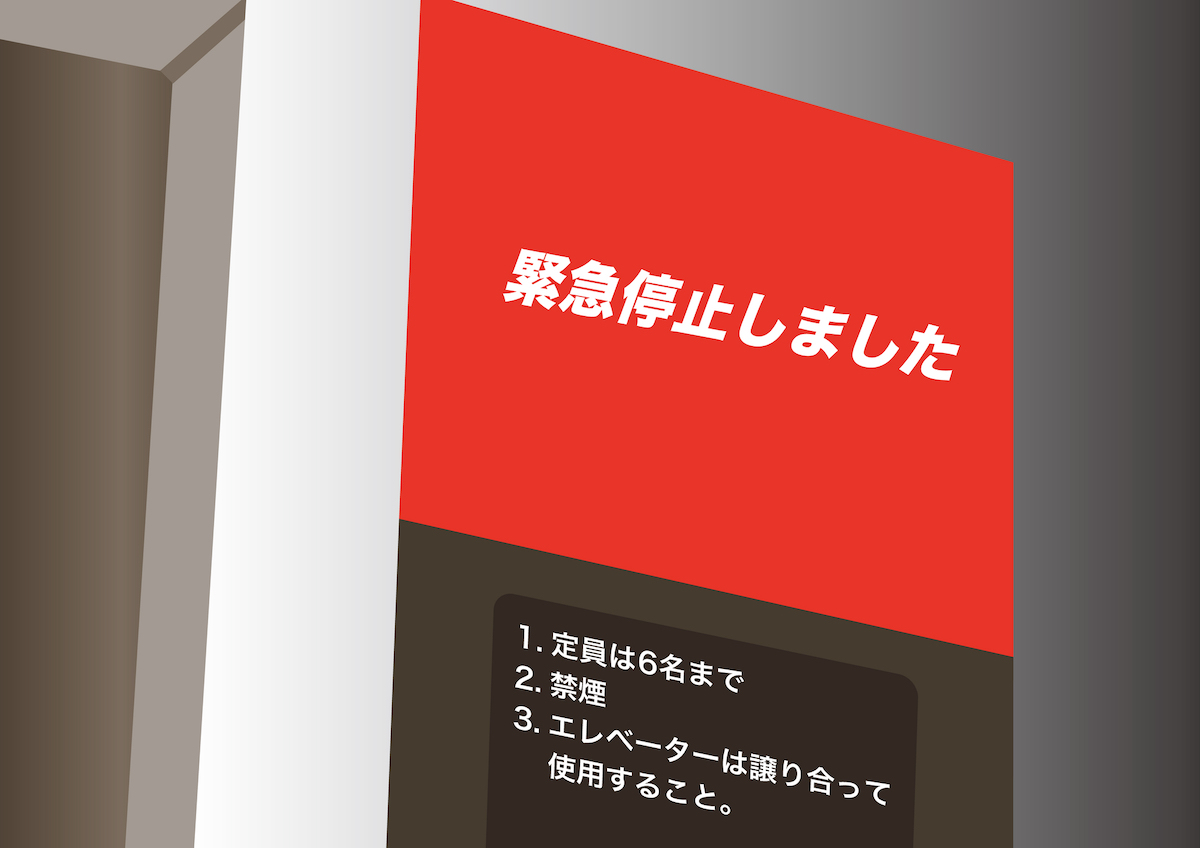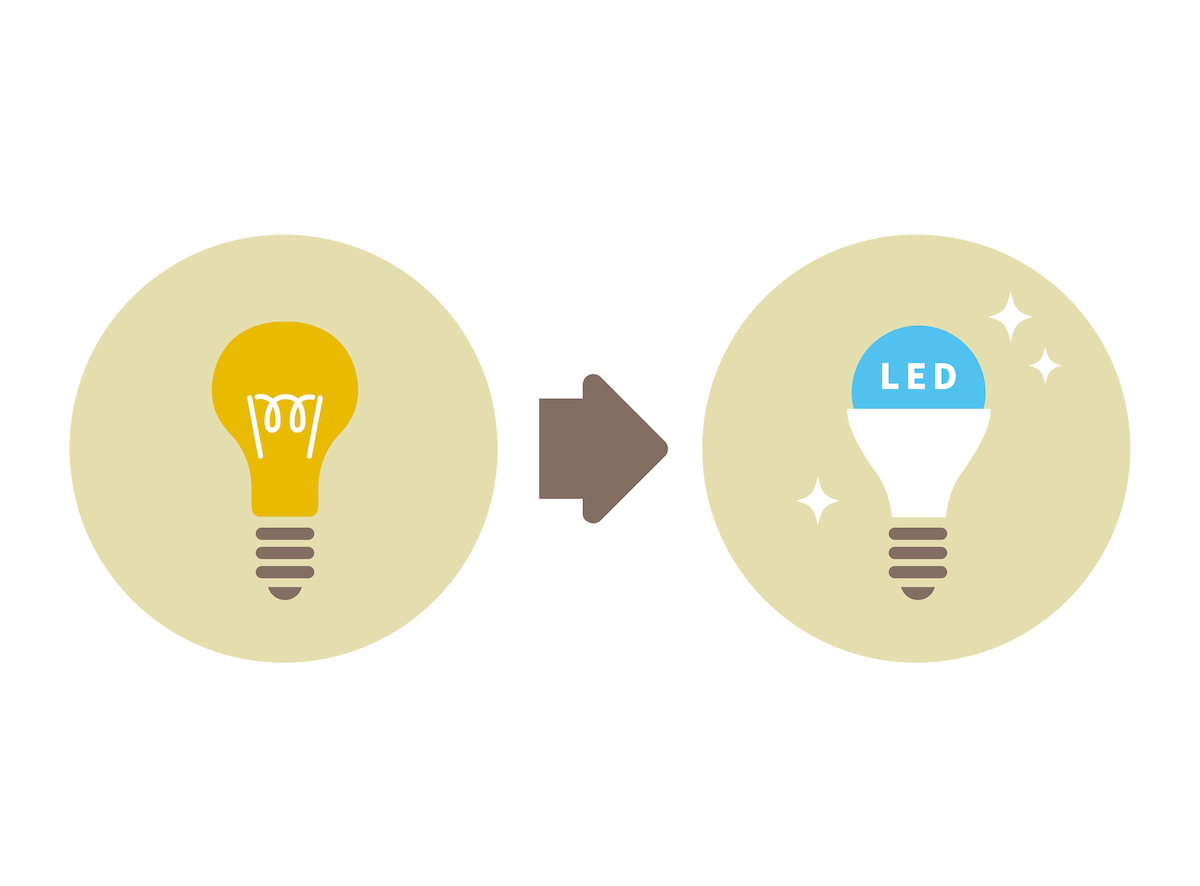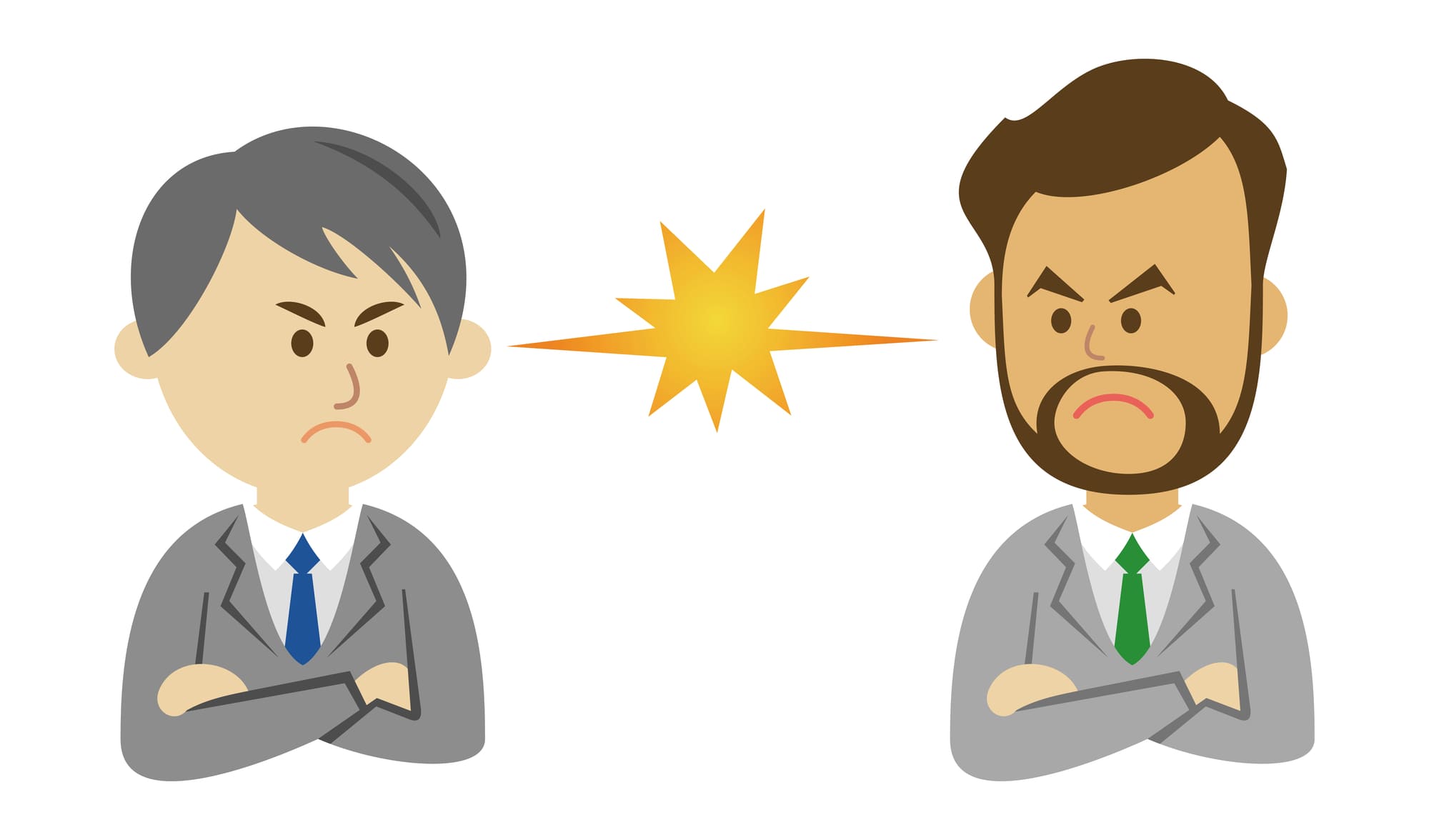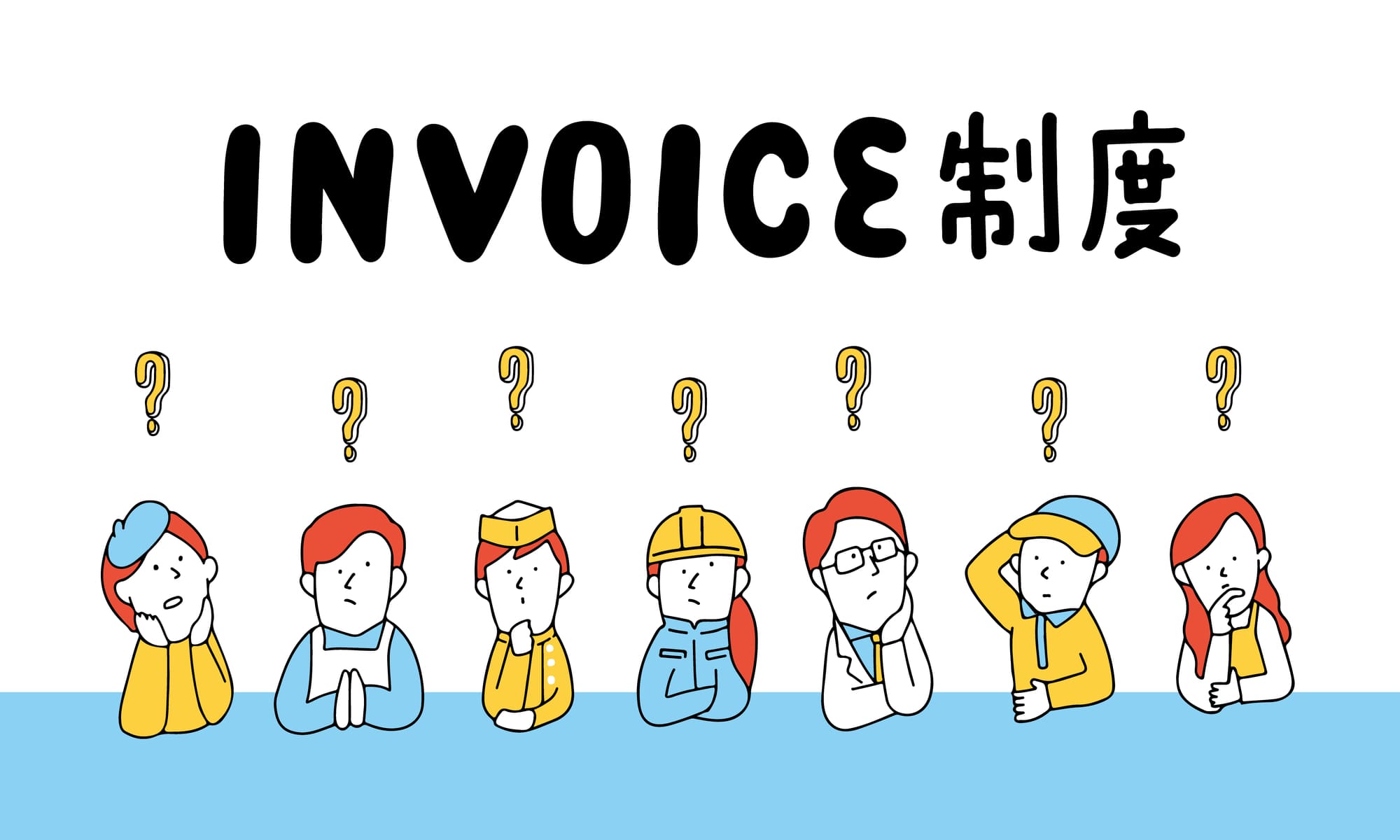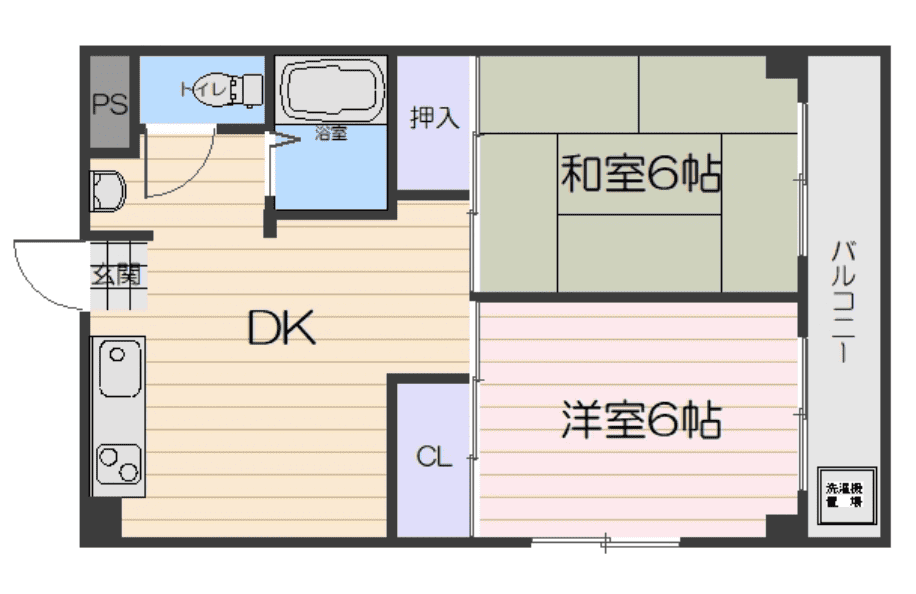「所有者不明土地」の実態とその影響
2017年の国土交通省の調査では「所有者不明土地」は全国土のおよそ22%、約410万ha相当の面積に及びます。
この面積は九州の面積(約368万ha)以上の土地に相当することから、所有者不明土地がいかに広大な面積であるかは理解しやすいのではないかと思います。
特にこの所有者不明土地の問題が顕著化したのが、東日本大震災の復興事業においてだと言われています。被災者の集団移転に伴う高台用地の取得に際し、所有者不明土地が含まれていたことで計画の変更や遅延が発生。土地の所有者がわからないことが、人の命や生活に関わる復興事業の局面で大きな問題となったことから、これを放置することはできないとの考えに至ります。
所有者不明土地が発生する原因の3分の2以上が、相続を受けた後に登記をしていない「相続登記の未了」だとされています。
今後、日本ではますます高齢化が進み、それに伴い相続の機会の増加が確実なため、この問題は更に深刻度を増すことから、是正の必要性が高まり今回の法案が成立することになります。
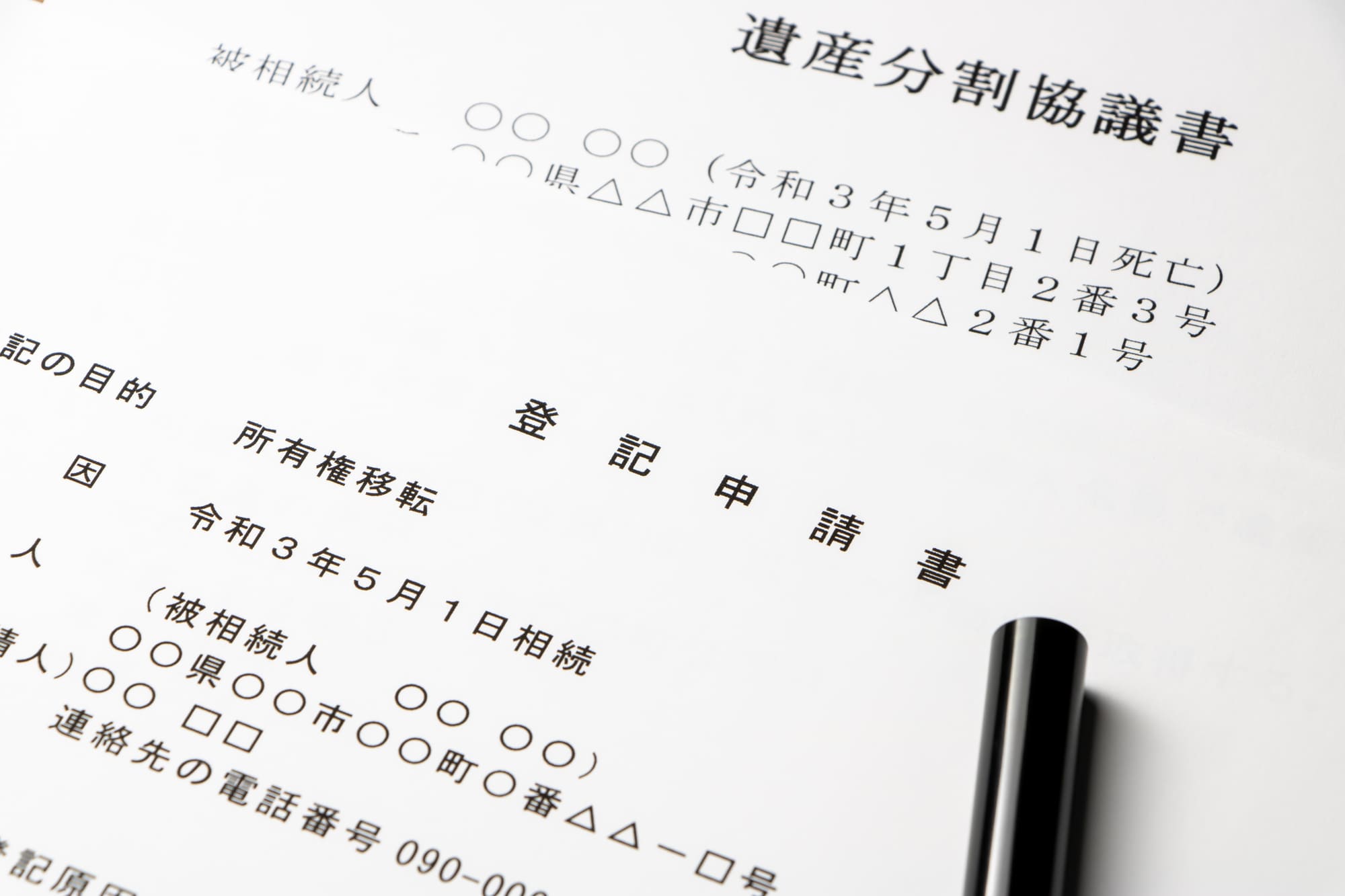
「所有者不明土地の関連法案」の3つのポイント
今回の法案は、所有者不明土地の【発生予防】と【土地利用の円滑化】の両面から見直しが行われており、次の3点がポイントになります。
ポイント①【発生予防】登記をさせる制度(不動産登記制度)の見直し
ポイント②【発生予防】土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設
ポイント③【土地利用の円滑化】土地利用に関連する民法の規律の見直し。
この【発生予防】と【土地利用の円滑化】の両面から法案の効果をみてみます。
ポイント①【発生予防】不動産登記制度の見直し
まず、所有者不明土地の発生原因である「相続登記の未了」の対策として法案が改正されています。
相続登記の義務化:2024年4月1日施行
今まで任意であった「相続登記」が義務化。不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内の登記申請が義務化、違反すれば10万円以下の過料が課される可能性があります。
相続人申告登記:2024年4月1日施行
登記の意思があっても、すぐに本登記ができない場合等の事情に配慮して、相続人は「自分は法定相続人の一人である」と登記所に申し出ることができ、相続人が単独でも申請ができるように変更。相続登記の申請義務を簡易にできるようにと改正。
住所変更登記の義務化:2026年4月までに施行
引っ越しから2年以内の登記申請を義務化。違反すると5万円以下の過料が課される可能性があります。さらに、登記官が住民基本台帳ネットワーク等、他の公的機関から情報を取得した場合に、職権で変更登記ができるようにする新たな仕組みも導入されます。
ポイント②【発生予防】相続土地国庫帰属制度の創設
土地を相続はしたものの手放したいと考える人は多く、時に十分な管理がされず、倒壊リスクを抱えた建物などが発生していることから改正されています。
相続土地国庫帰属制度の創設:2023年4月27日施行
相続により取得した土地を手放して国庫に帰属させることができる制度。しかし、権利関係に争いがある場合や、土壌汚染等がある場合は対象外となります。
申請後、法務大臣の要件審査・承認の後、土地の所有者は10年分の管理費相当額を国に支払うことで国庫帰属が可能となります。

ポイント③【土地利用の円滑化】民法のルールの見直し
所有者(共有者)不明土地の利用制度:2023年4月1日施行
所有者(共有者)が不明の場合、同意や意思決定ができない問題が発生します。そんな場合、裁判所の関与の下、不明者に対して公告等の手続きを行えば、残りの共有者の同意で、共有土地の処分や利用を行うことが可能となります。
管理不全土地等の管理制度:2023年4月1日施行
十分な管理がされず放置されている場合、土地の荒廃や建物倒壊などのリスクが高まります。今回の改正で、一定の手続きのもと、裁判所が所有者不明土地等の管理に特化した管理人を選任できる制度が創設されます。
まとめ
今回の施行により、土地所有者は「知らなかった」や「忘れていた」では済まされなくなります。土地を相続や売却で取得した場合は、必ず登記を行う義務、住所変更登記も義務化されたので注意が必要です。
土地所有者の対処すべき義務が増えることになりますが、その結果、不明土地が原因でストップしていた再開発案件が前に進むことや、地方の山林等で所有者不明となっている土地に対してアクションが取りやすくなることから、公共事業の促進につながり、地方活性化や、地域課題の解決につながることが期待されています。