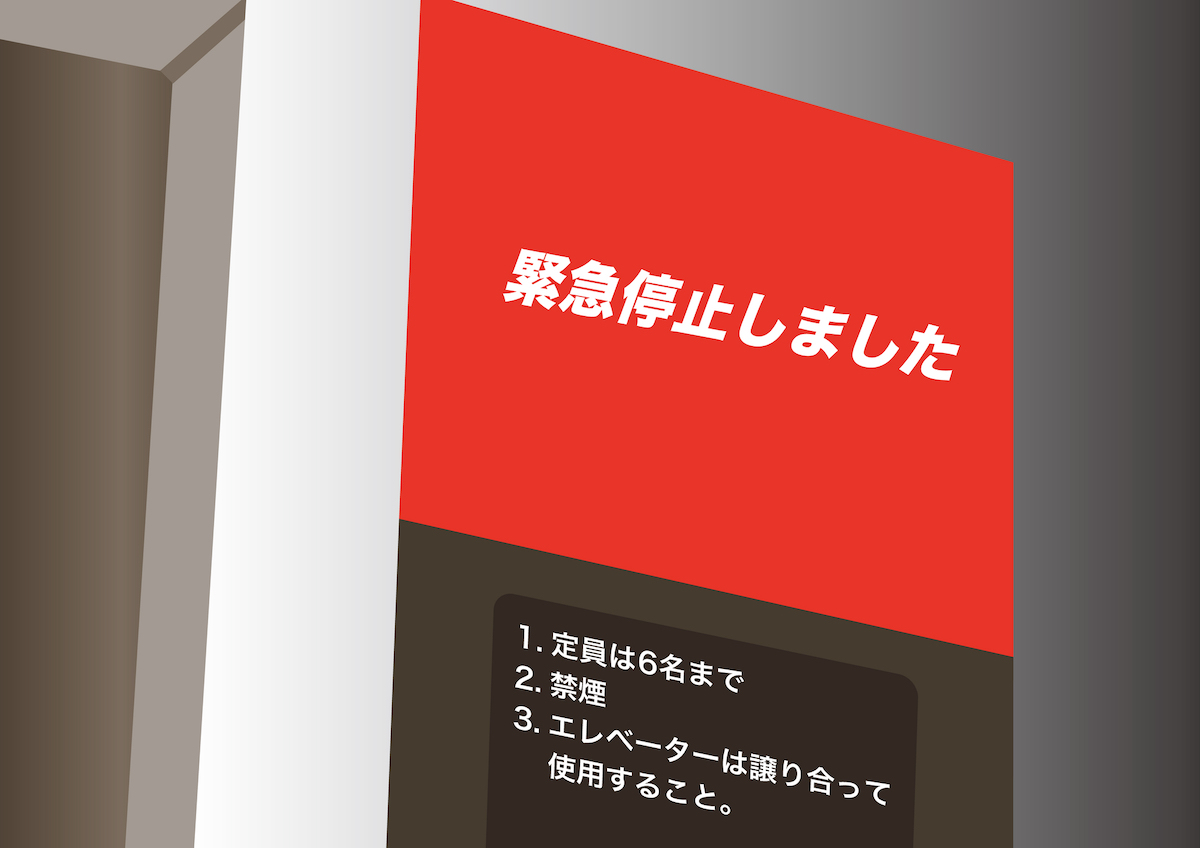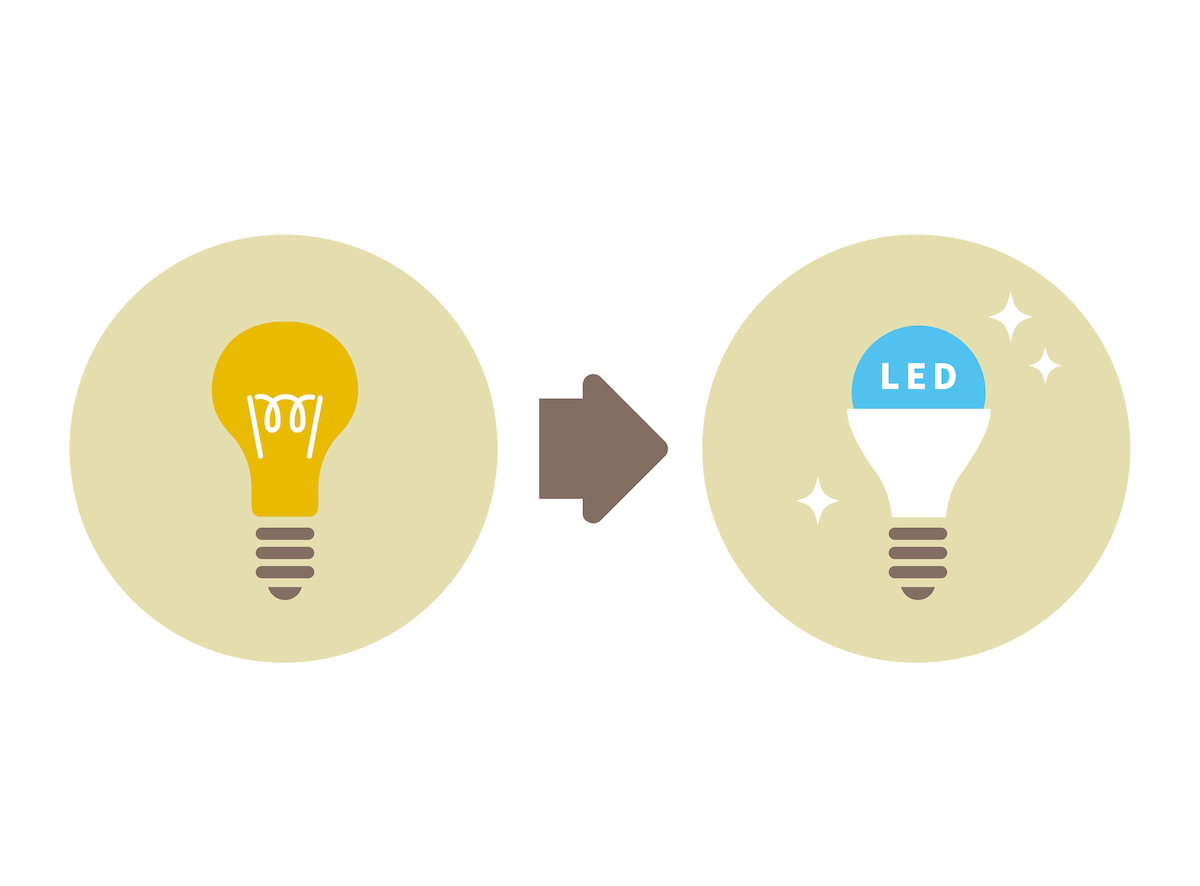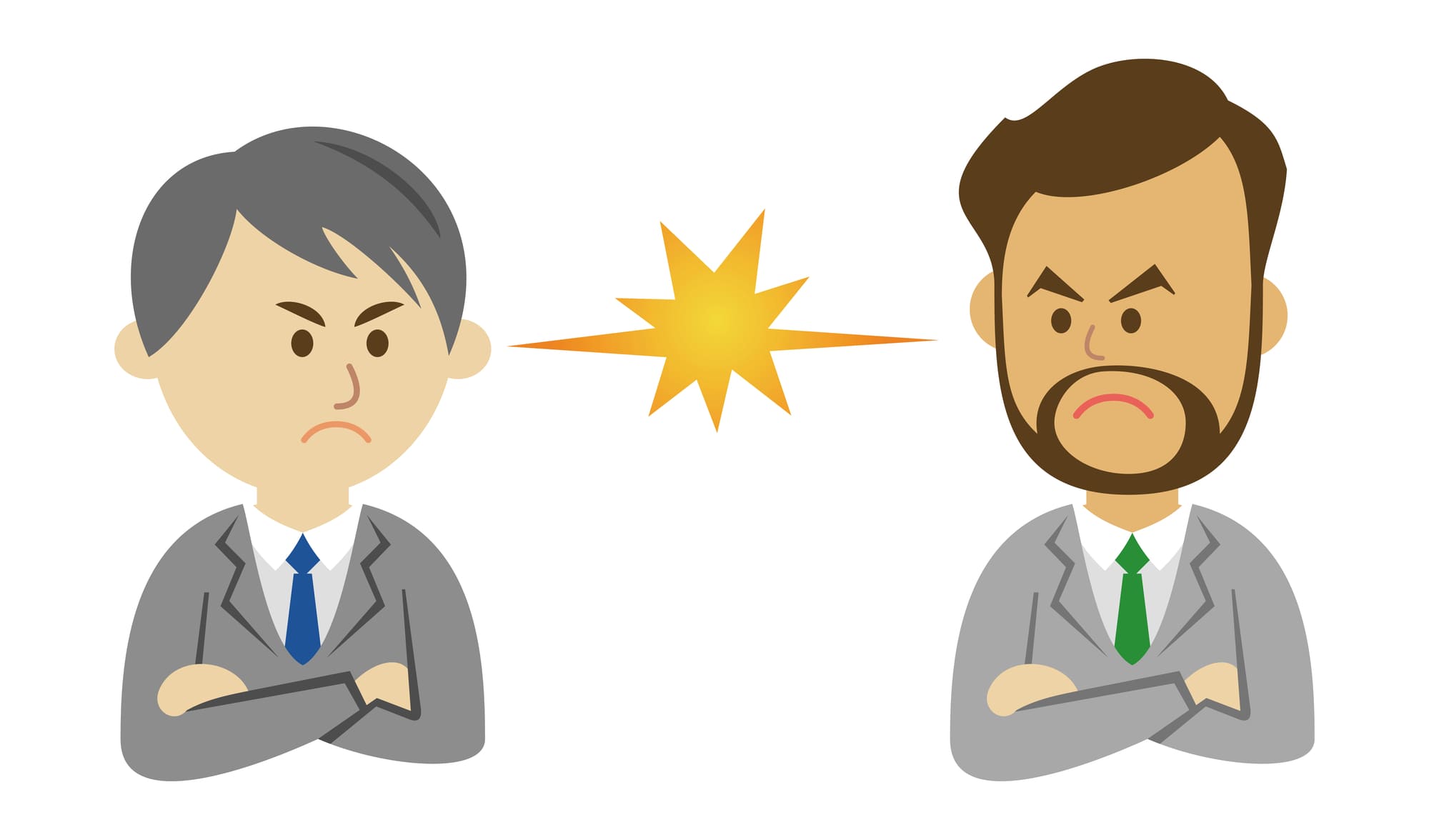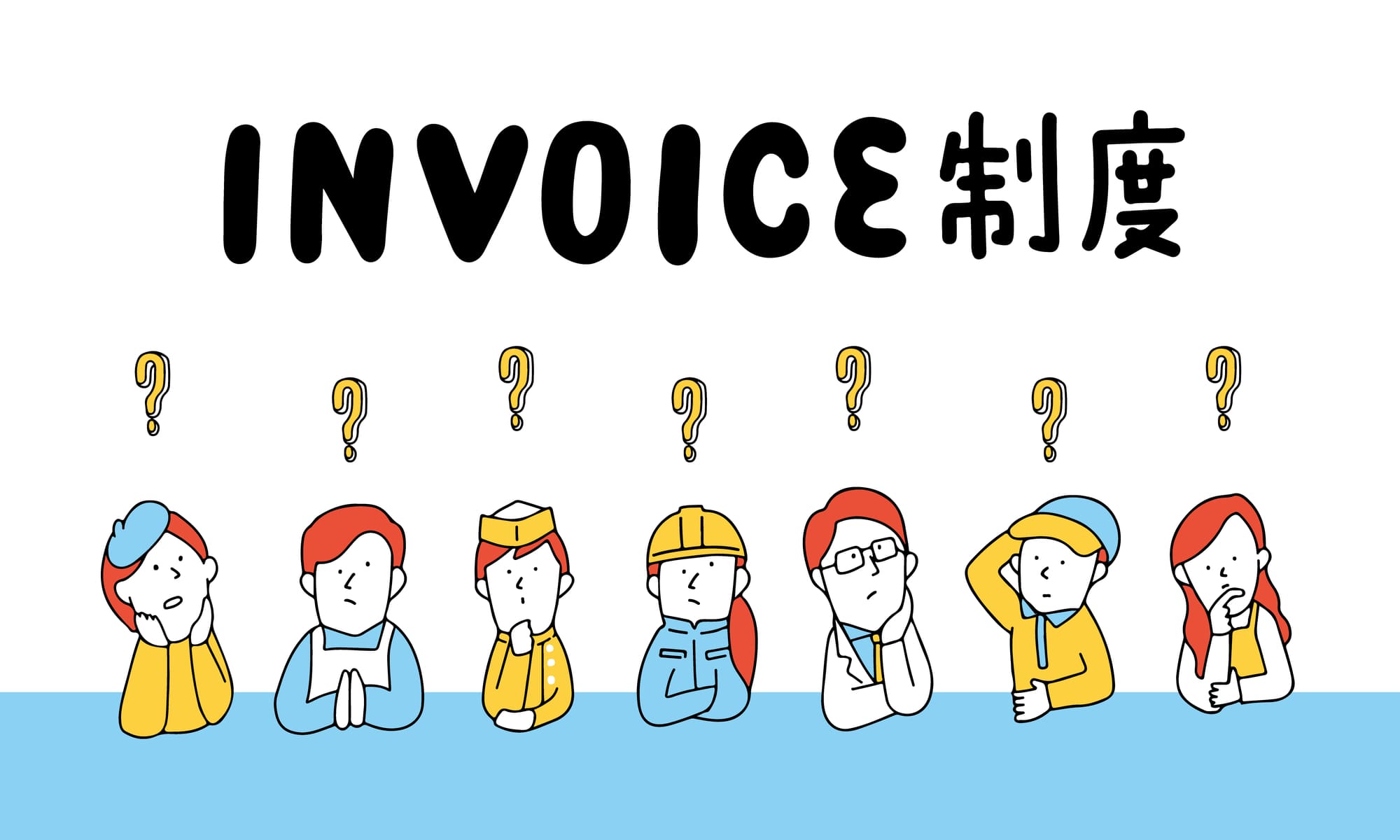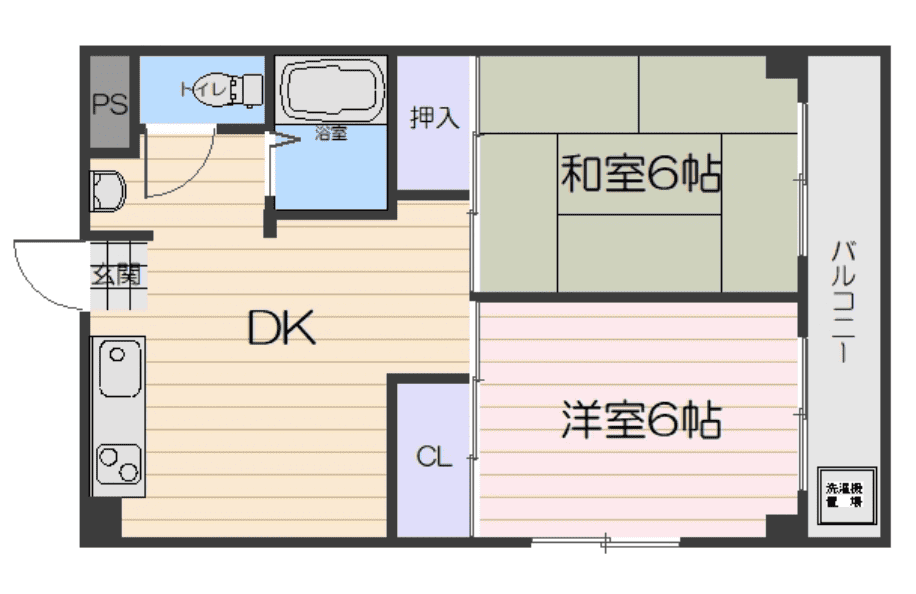ポンプの種類
マンションに水を供給する方法には4つあり、その内、ポンプが関係するのは、以下②③④の3つの方式の場合になります。
①直結給水方式
浄水場から送られてくる水の圧力をそのまま利用して各部屋へ給水する方式。この給水方式では、ポンプは使用しません。
②直結増圧方式
配管から送られてくる水の圧力を、「増圧ポンプ」で圧力をプラスして各階にあげて各部屋におくる方式です。
③受水槽方式
配管から送られてくる水を一旦貯水槽タンクに貯水し、「加圧ポンプ」で各部屋におくる方式です。
④高架水槽方式
配管から送られてくる水を一旦貯水槽タンクに貯水し、「揚水ポンプ」で屋上に設置した高架水槽に送り、その水を自然落下させて各部屋に送る方式です。
※ちなみにポンプにはこの他、排水ポンプがあります。地下に雨水槽や汚水槽がある場合は、
排水ポンプで水をくみ上げる役割をするポンプがあります。
こうした各種ポンプが何らかの理由で故障し動かなくなると「断水」が発生します。突然、全ての部屋の水が出なくなる事態が発生します。
しかし、マンション等の給水設備では簡単に断水を起こさせないため、多くの場合ポンプは2基設置されています。これはたとえ1基が壊れても、もう1基で稼働させ、修理や交換までの間に断水せず、水を供給できるようにしています。また交互運転をさせることで、1基のみの連続稼働でかかるポンプへの負担を軽減し、故障頻度を下げることになります。

ポンプの修理、交換ができないという事実
ポンプが何らかの理由で稼働しなくなると、「水がでない!」と入居者さんから連絡が入ります。その一報からすぐに次の対応を実施します。
① 水道局に連絡、その地域で断水が発生していないかの確認。
↓
② 地域断水がない場合、断水原因の調査。
↓
③ 原因がポンプの場合、2基のうち稼働できるポンプのみで稼働させ、断水を一時的に回避。
↓
④ 故障したポンプの修理・交換検討と施工実施。
通常時であれば、④までの施工を段取りよく実施することで、断水の期間を極力短く対応することが可能でした。しかし、今般の大きな問題は、その修理や交換をするためのポンプ本体や周辺機器が、世界的な半導体・電子部品の供給難や運送遅延などの影響で、発注してから納品までに数カ月必要な状況にあるということです。
③の断水回避の対応で、一時的に片側1基のみの稼働で断水を回避することはできますが、両基とも製造は同時期であり、同じ故障原因をかかえていると見ておかしくありません。その状況下で、負担のかかる1基のみでの連続稼働をさせるわけですから、もう1基もいつ故障してもおかしくない状況になります。
供給不足から修理や交換までに時間を要し、2基とも故障して動かないという事態の発生が現実味を帯びています。

断水発生は経営危機につながる
最も恐ろしい事態は、ポンプが2基とも故障し、マンション全体が断水状態に陥ることです。
貸主は、借主に賃借物を使用収益させる義務があります。賃借人にきちんと生活ができる住まいを提供する義務があるわけです。その対価として賃借人は賃料を払います。よって断水で水が使えない場合、適切に居住できる環境を提供できる状況にはないと判断されるので、当然ながら賃料減額等の対応が必要となります。
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が作成した「賃料減額ガイドライン」では、具体的に水が使えない場合、免責日数は2日間、賃料の30%の賃料減額と示されています。
更に、通常時であれば、早期にポンプの修理、交換を実施することで断水を回避しその損害を小さくはできますが、部品の供給不足から、修理、交換をしたくてもできない状況にあり、長期的に断水が継続すれば、30%の減額だけで賃借人が納得するとは考えにくく、住めない状況による損害賠償請求などがマンションの全部屋で発生する事態が想定されます。こうなってしまうと、健全な不動産経営が不可能になります。

断水リスク対策
こうした断水にかかる不動産経営のリスクの回避対策には、早期のポンプ修繕・交換の対応が有効な対策と言えます。
まず、所有物件のポンプの設置状況をチェックしてみてください。その時にポンプタイプと製造年月日を確認し、ポンプの稼働音と水漏れなど異常がないかのチェックです。
稼働音が大き過ぎたり金属音がしていたり、水漏れがあれば、どこかで異常が発生しているため、早急に水道業者やポンプメーカーに点検を依頼する必要があります。また、異常がない場合でも、費用はかかりますが、専門業者による定期的なポンプの点検の実施は有効ですので検討してみてください。異常が発見された場合には、積極的にオーバーホールや修理の実施、早めの交換の実施を検討してください。
お伝えしてきました通り、ポンプ本体・周辺部品等の納期遅延から、断水が継続してしまう事態は、不動産経営の継続が不可能になる事態を招く恐れがあります。予防対策、断水へのリスク対策として早期に積極的な設備の更新が必要であることをご理解ください。