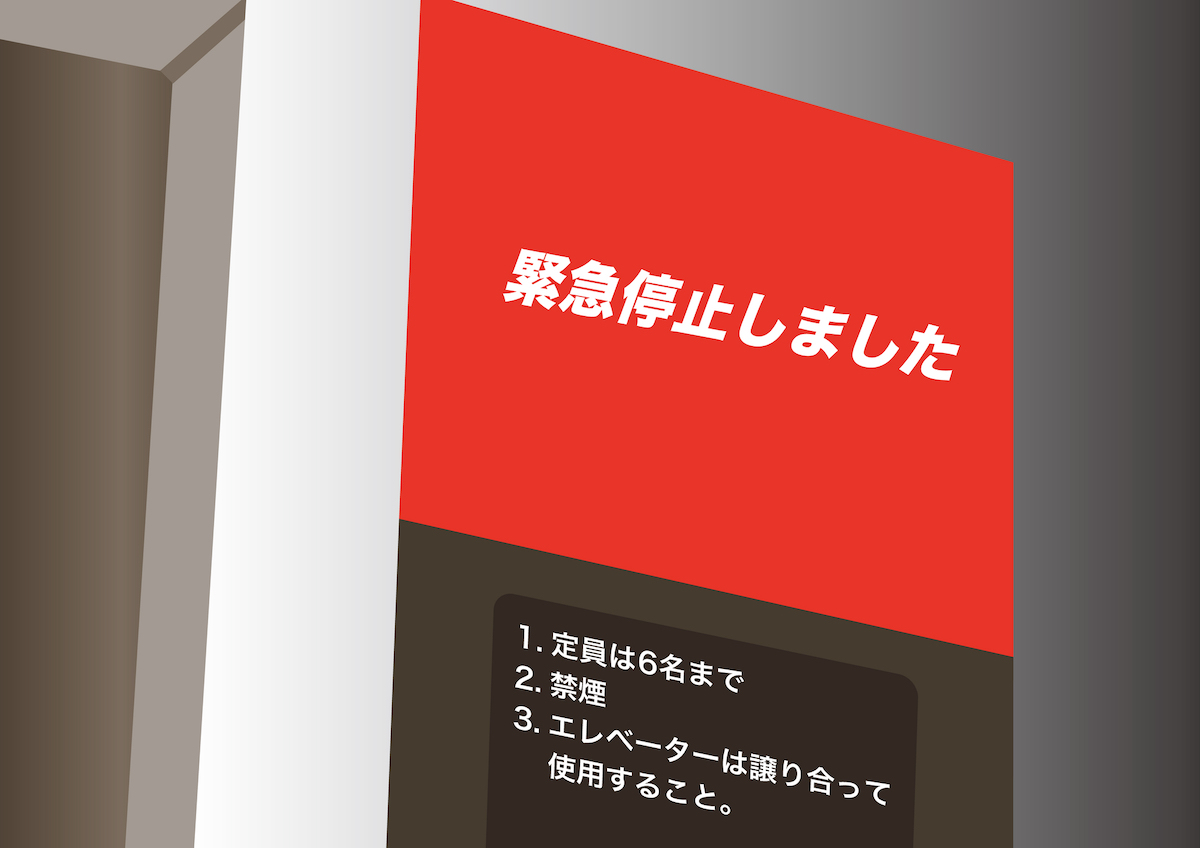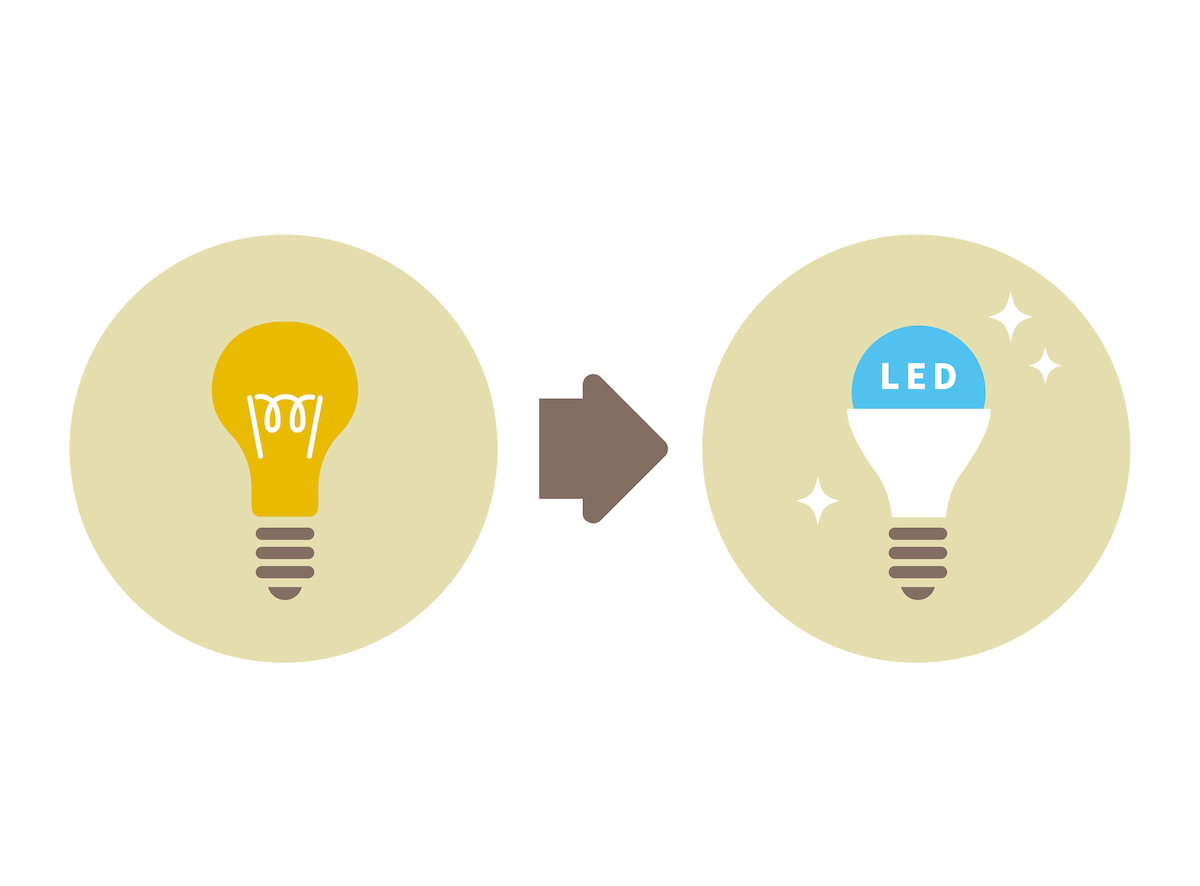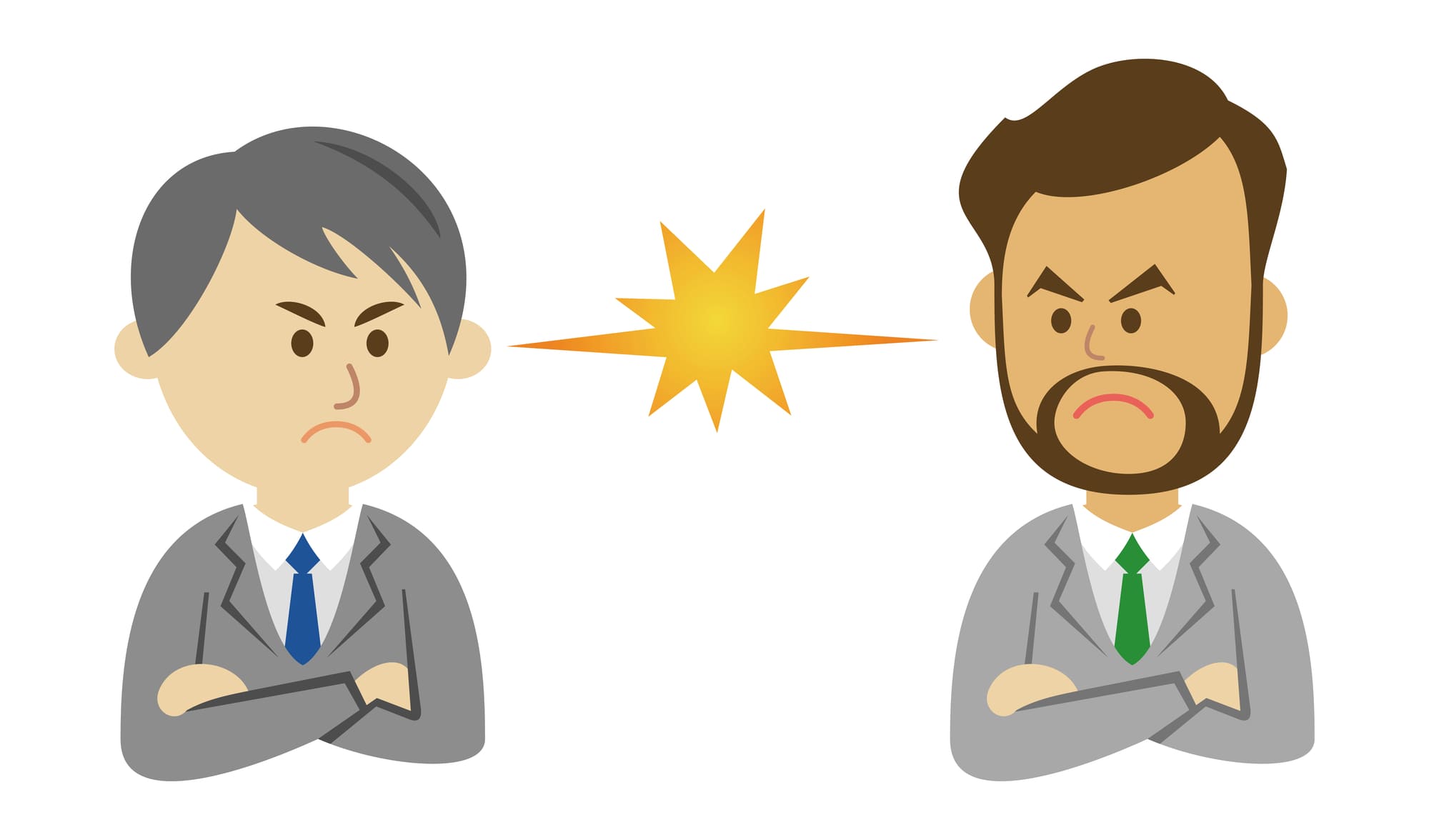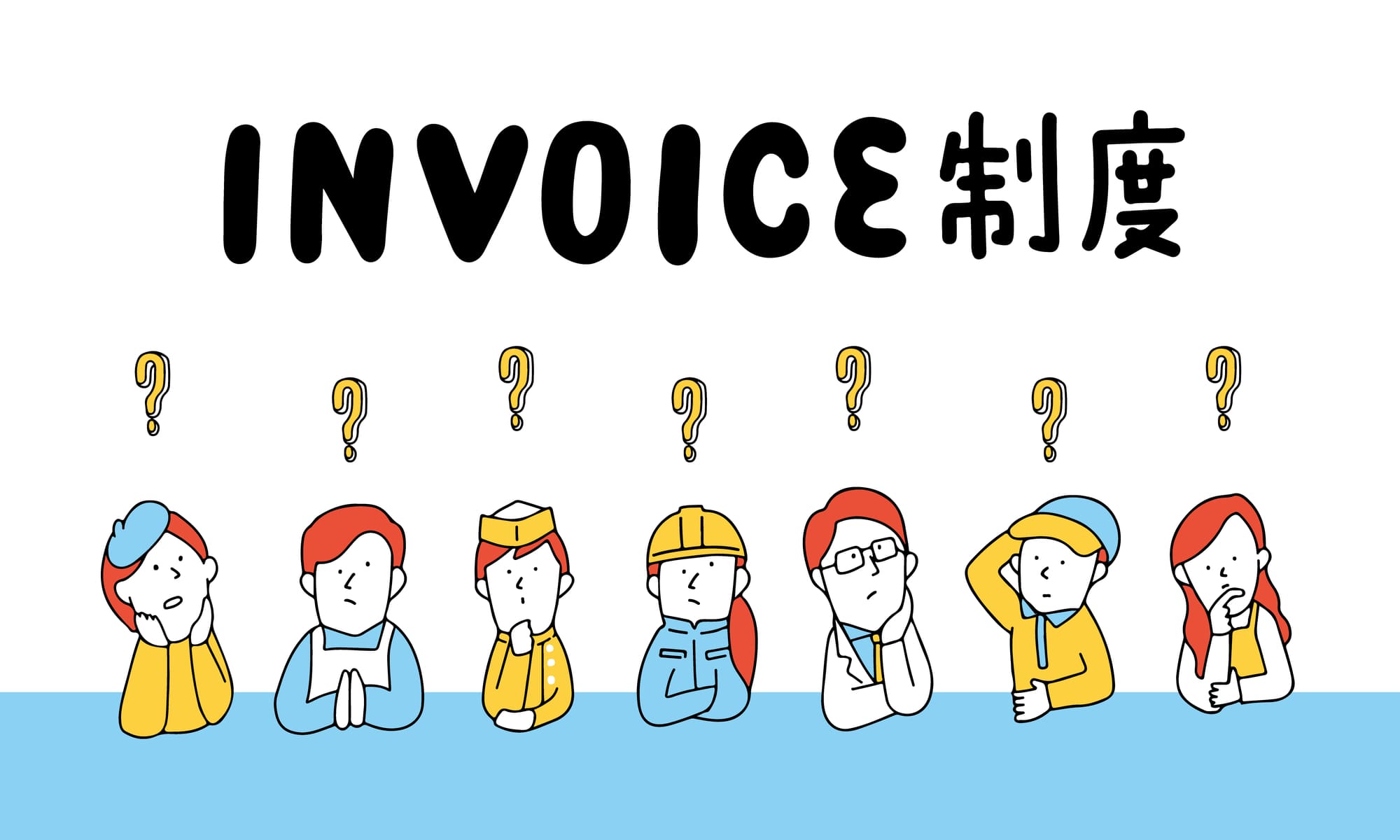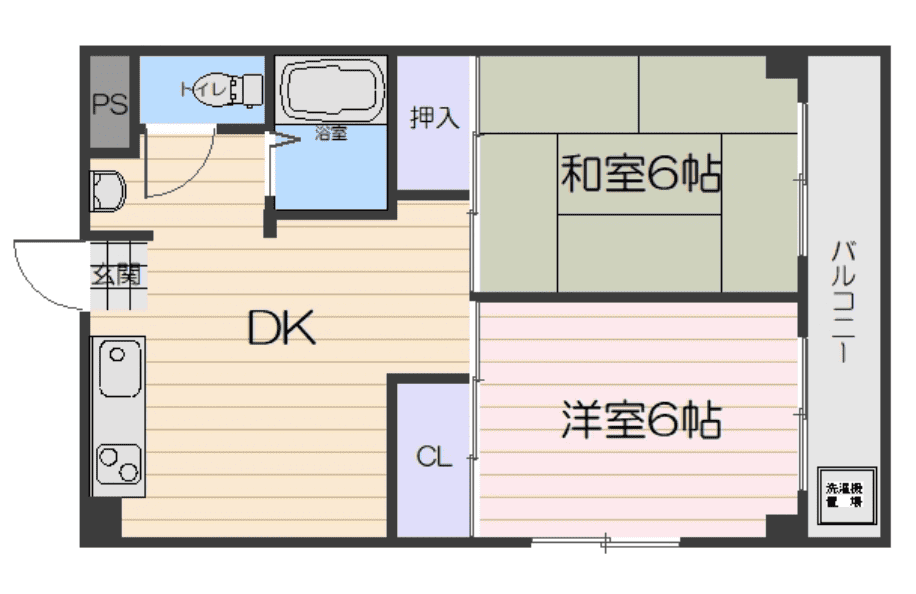インボイス登録が済んだ後
インボイス発行事業者への登録を済ませた後、何をどうすればいいか?と当社にもお問い合わせをいただいています。
賃貸事業における登録後の対応については情報がまだまだ少ないようです。

まず、インボイスを発行する際には、正確に契約内容や税率、税額を伝えるために決められた事項を記載する必要があります。
しかし、賃借人から賃料を受領する場合、定額の賃料であれば多くの場合、口座振替などを利用し、都度の請求書発行は省略していると思います。
都度、請求書を発行していない場合、どうしたらいいの?という声が大半です。
そのためにすべき対策がありますが、それをお伝えする前にまず、インボイスに必要な記載事項についてみてみます。

インボイスに必要な記載事項
インボイスに必要な記載項目は以下の6点になります。
①インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載)
④税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
⑤消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
これを賃貸事業に置き換えるとこうなります。
①発行者である オーナーさまの名称と登録番号
②取引年月日 → 賃料の場合は支払日や請求日
③取引の内容 → 賃貸借の内容
④税率ごとの対価の合計額及び適用税率
⑤消費税額等
⑥相手事業者の氏名または名称 → 賃借人の名称
この6点が記載された書面などを課税事業者である賃借人は保存しておく必要があります。
6点すべてが記載されている必要がありますが、ひとつの書類にまとまっていることが必要なわけではありません。複数の文書で記載事項を満たせばいいことになります。
例えば、既に締結中の契約の場合、賃貸借契約に①の登録番号の記載は当然ありませんが、③の賃貸借に内容や⑥の借主の名称は記載されています。この場合、新たに契約書を締結し直す必要はなく、6つのうち不足している事項を通知し、賃借人がその文書を覚書として保存すればインボイスとして利用することが可能になります。
つまりは、【インボイス=請求書】だからといって、必ずしも請求書の体裁である必要はなく、6つの事項が不足なく賃借人の手元で保存されていれば問題ありません。
ちなみに新規契約の場合は、②の取引年月日以外を予め賃貸借契約書に必要事項を記載しておくことで対応することができます。※②は支払日がわかる通帳のコピーの保存で対応できます。
賃借人への必要事項の通知は、覚書として不足しているインボイスの登録番号や適用税率等を記載し通知書を作成したのち、インボイスが必要であろう賃借人を選定し郵送等すれば、賃貸オーナー側の手続きは完了です。
委託中の管理会社がある場合、依頼すればこのあたり全て対応してくれるとおもいます。

登録申請期日が延長
インボイス制度開始の10月に間に合わせるためには、2023年の3月31日までに登録申請が必要でしたが、これが実質、2023年9月30日まで延長になりました。
申請までに時間の余裕が生まれたわけですが、少し注意が必要になります。
登録申請が受理されてから番号取得までには時間を要します。
番号取得まで現状で1~1.5ヶ月必要になります。
これから申請が本格化することを考えると更に時間がかかることが想定されます。
10月からの適用スタートを考えるなら、登録申請後の処理を想定し、延長になったといえど、ギリギリではなく早めの登録申請が必要だという認識をお持ちください。
軽減措置について
インボイス制度の実施後に、インボイス発行事業者でない賃貸オーナーからの請求で支払いをしたテナントである課税事業者は、仕入れ額控除ができずに消費税負担が増えることになります。
そのため賃料値下げ交渉や、退去の可能性が含まれると考えられています。
しかし、インボイス発行事業者でない賃貸オーナーからの請求について、実施後6年間、一定割合が控除可能な軽減措置が取られます。
軽減措置内容
インボイス制度実施後
・3年間は80%控除可能
・その後更に3年間は50%控除可能
この軽減措置があることから当面、賃料値下げ交渉や退去の可能性は低いのではとの考えもあることから、免税事業者である賃貸オーナーの判断は難しいところです。
税務的な判断になることから顧問税理士や不動産経営に明るい税理士にご相談ください。