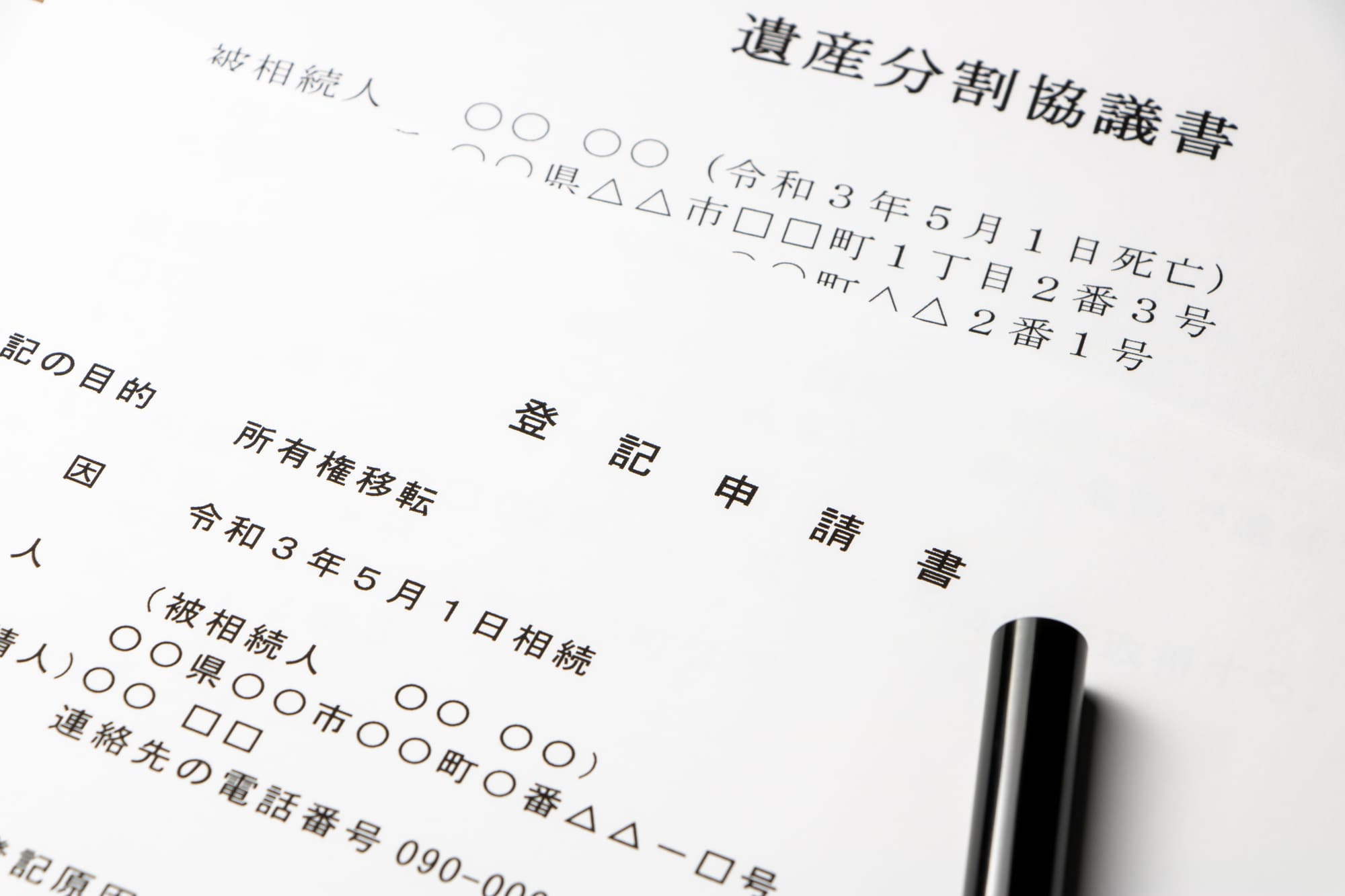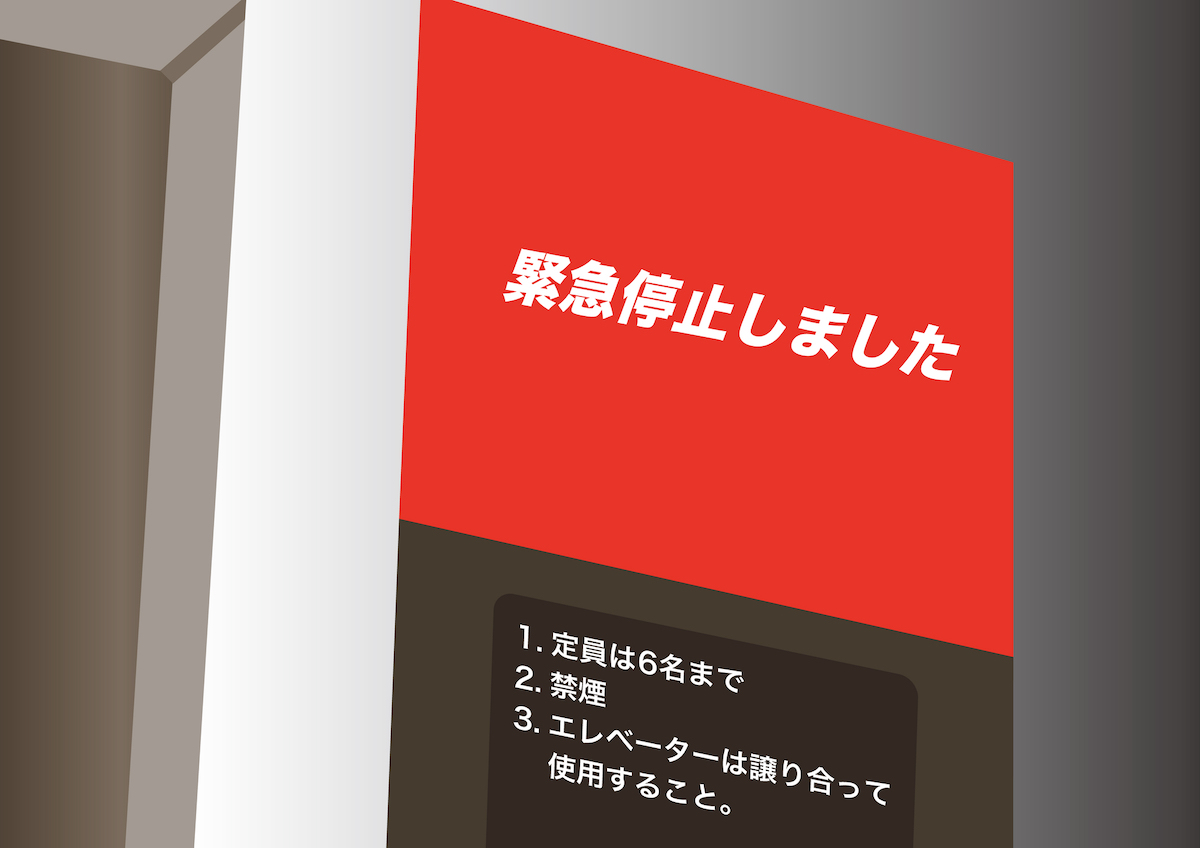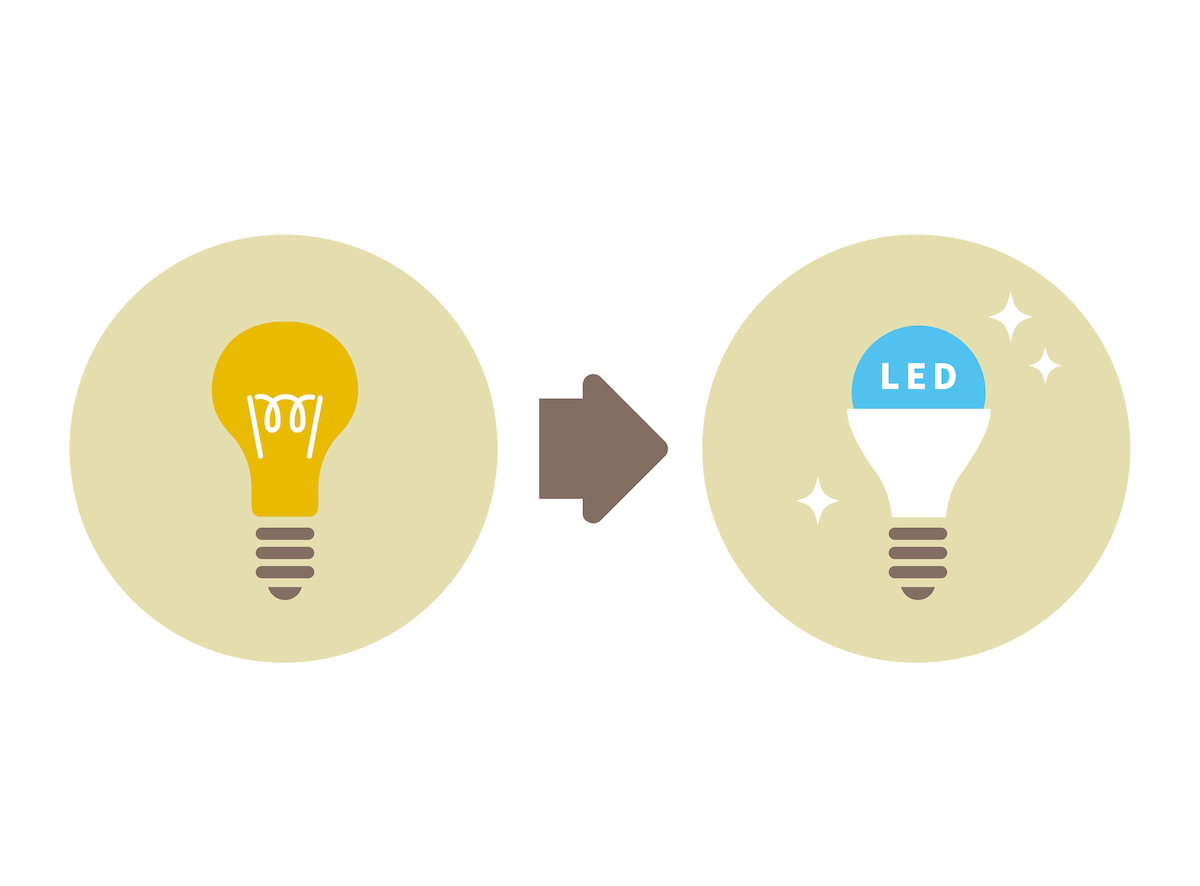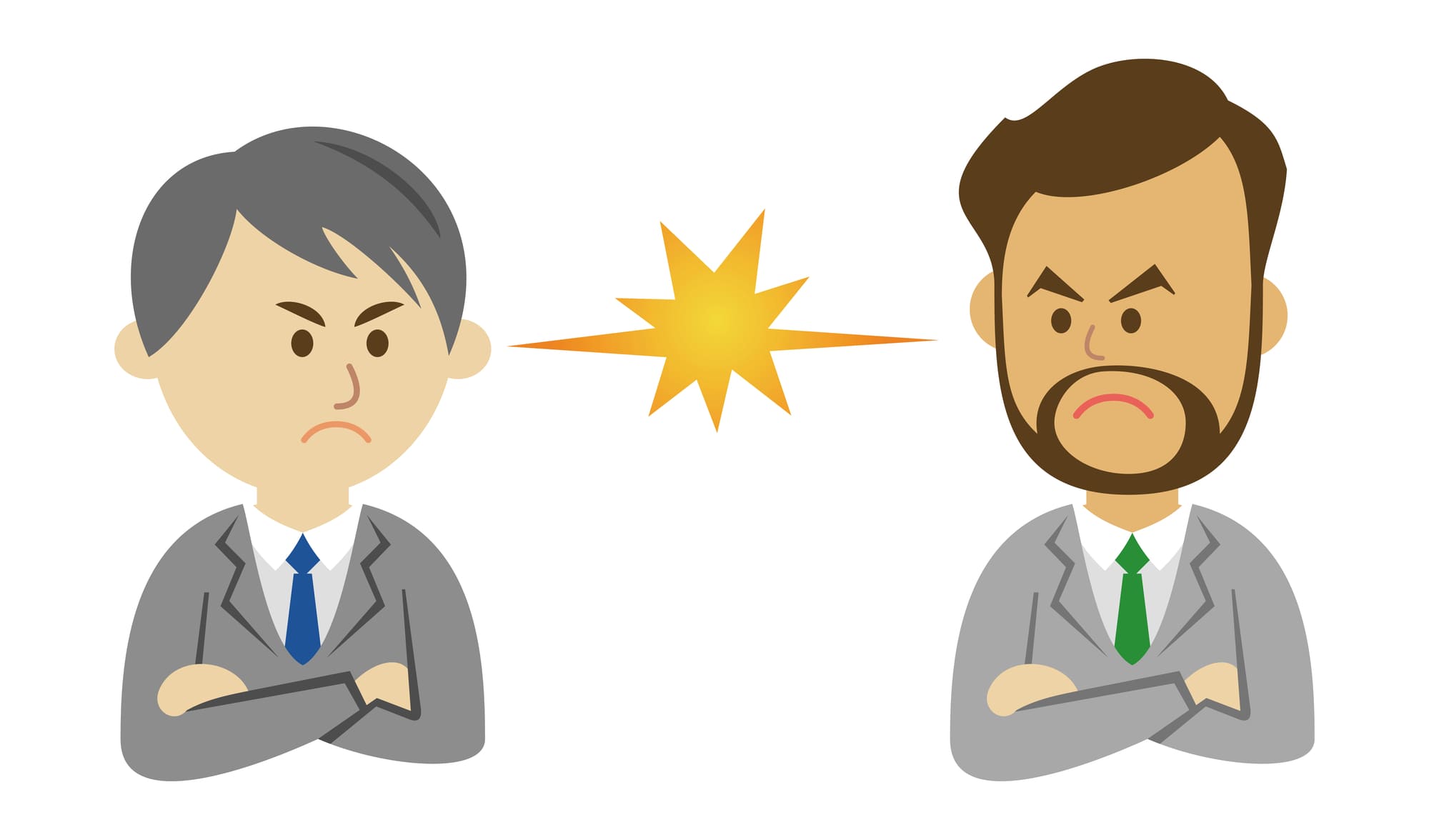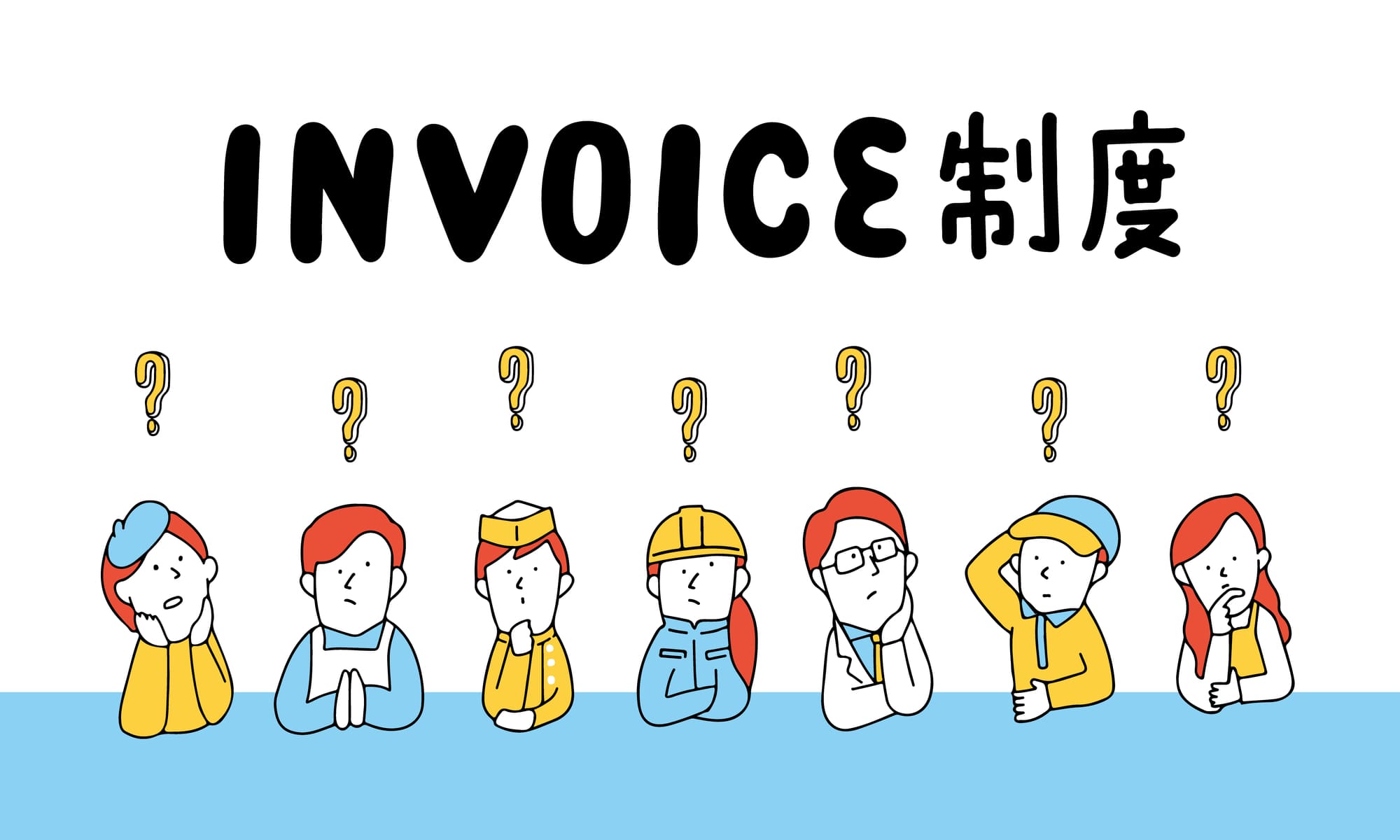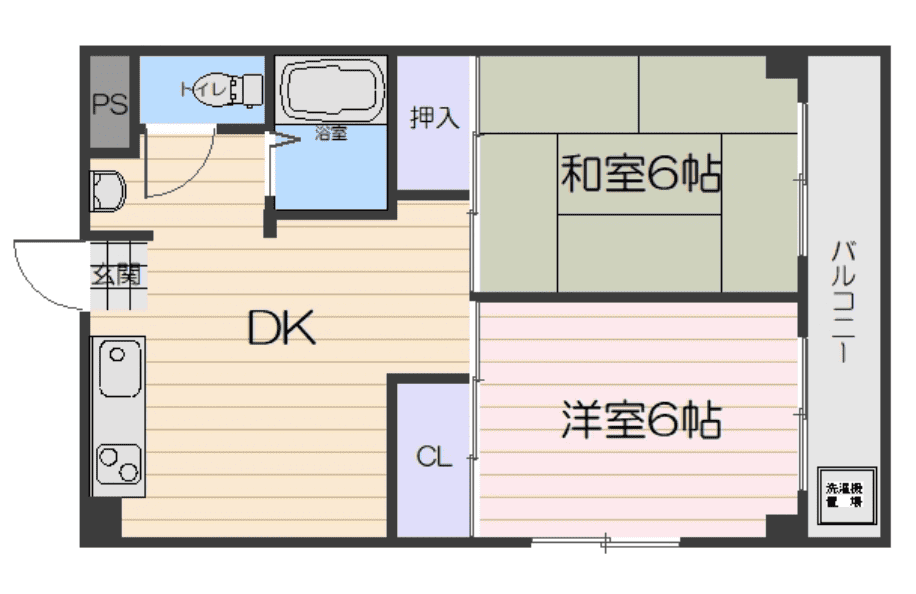なぜ義務化されるのか?
所有者不明土地の最大の原因が相続登記にあることが問題視されていることによります。
日本全国の所有者不明土地は、全国土のおよそ22%に及び九州全体の面積以上あると言われ、この不明土地発生の6割が相続登記の未了が原因となります。
今後、更に高齢化が進む日本において、相続発生の増加は避けられないことであり、このままでは未登記の不動産が更に増え続けることが想定されるため、その是正のために相続登記手続きが義務化されることになりました。


義務化で変わるルールと違反時の罰則
相続によって不動産を取得した相続人が、その取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないと定められました。
被相続人が亡くなったことを知らなかった場合や、被相続人の遺産に不動産が含まれていることを知らなかった場合には、それらのことを知った日から3年以内となります。
あくまで「被相続人の死亡を知った日」からではなく、「不動産の取得したことを知った日」なので、取得したことを知らなければ3年の期間はスタートしないことになります。
これまで「相続登記」がなされてこなかった原因として考えられるのが、相続登記の申請が任意であることが前提として
①申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少ないこと。
②相続した土地の価値が小さかったり、その土地の売却が困難である場合に費用や手間をかけて登録申請する意味が見いだせないこと。
この2点が原因だと考えられます。
しかし今回の義務化で、「相続登記」をしないという選択肢は原則なくなり、正当な理由なく違反した場合には、10万円以下の過料が課される可能性が発生します。
※過料とは:行政罰の一種で「罰金」とは異なる。過料の場合は前科がつくことはない。
3年以内に登記できない場合の対処法
相続は、時に「争族」と揶揄されるほど親族間で争いが起こり、遺産分割協議がうまくまとまらないケースが少なくありません。「争族」となった場合には、長期に紛争が続くこともあり、期限の3年以内に分割協議がまとまらない場合を想定した「相続人申告登記制度」の創設が予定されています。
遺産分割協議がまとまるまでの間は、法定相続分で共有された状態となります。うまくまとまらないので、共有状態を反映させた「相続登記」をしようとする場合、法定相続人の範囲や法定相続人の割合を確定させないといけないため、すべての相続人が把握できる資料が必要になったりとこれが大変です。

相続人申告登記制度で対応できる!
今回創設される「相続人申告登記制度」では、法定相続人が、法務局に対し、自身が被相続人の相続人である旨を申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することが可能になり過料が課される心配はなくなります。
この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、相続人持分の割合が登記されるわけではないので、全ての相続人を把握するための資料は必要はなく、相続人ひとりでも申告が可能になります。
ただし、相続や遺産分割が終了し、所有関係が確定した場合には、改めて「相続登記」をしなければならないことに変わりはありません。遺産分割協議が成立した日から3年以内に、登記申請が必要になり、これに違反した場合も過料の対象となります。
過去の相続で未登記の場合は?
今回の相続登記の義務化では、これまで放置されていた不動産に対しても義務付けされることになります。
しかし、この2024年4月1日の相続登記義務化と同時に、これまで放置されていた分までも義務違反となるのはあまりにも性急すぎるということから、既に相続が発生しているものの、未登記のケースでは、2024年 4月1日から3年以内に相続登記をするよう義務化されます。
つまりは、2027年3月31日までにこれまでの相続不動産においても相続登記を済ませておく必要があるわけです。
まとめ
所有者不明土地の是正解消策のひとつである「相続登記の義務化」ですが、10万円以下の過料の罰則で「どこまでの強制力があるのか?」と疑問視する声もあります。
しかし、相続登記を放置した後に起こる相続の複雑化などの問題や、土地の適切な管理や利用の妨げになることや、再開発災害の際の復旧公共事業に支障をきたすため、適切な登記の履行は必須であり、相続登記の義務を果たす必要性を軽視することはできないと考えられます。