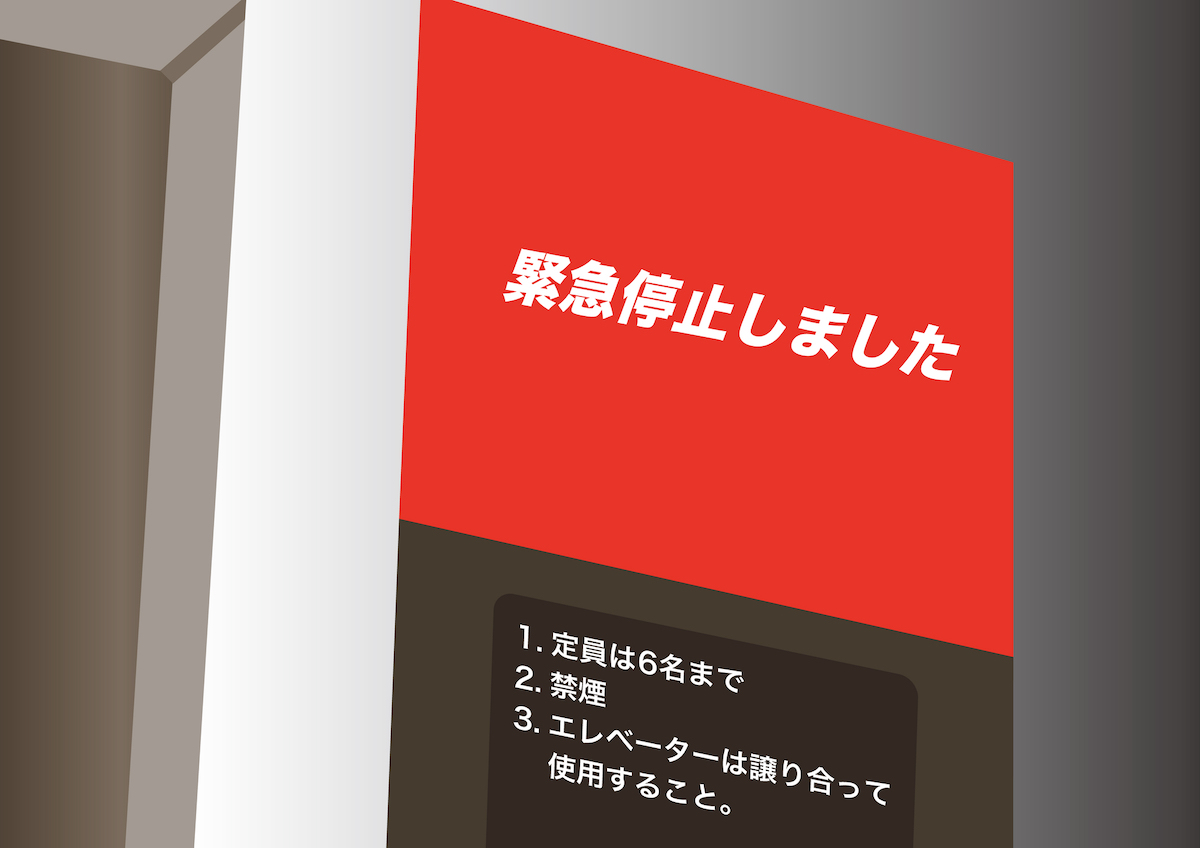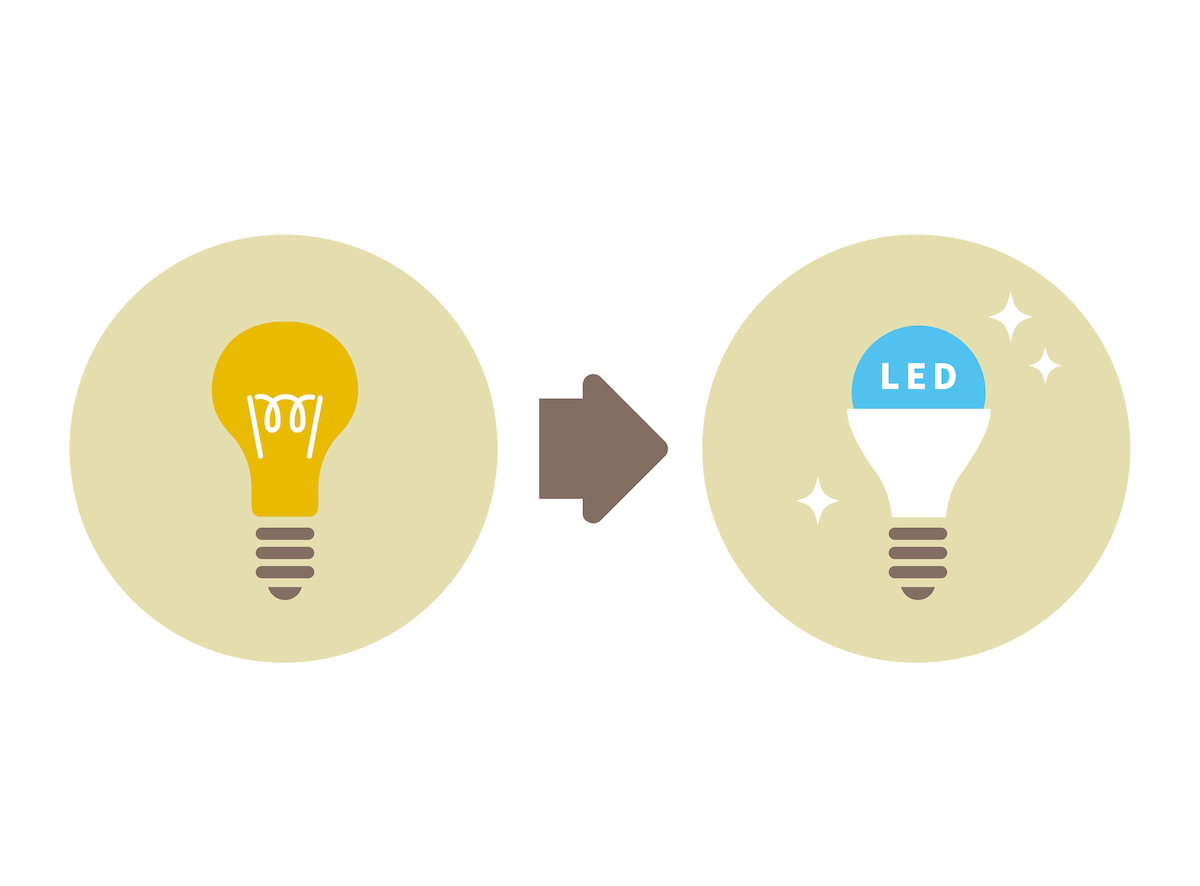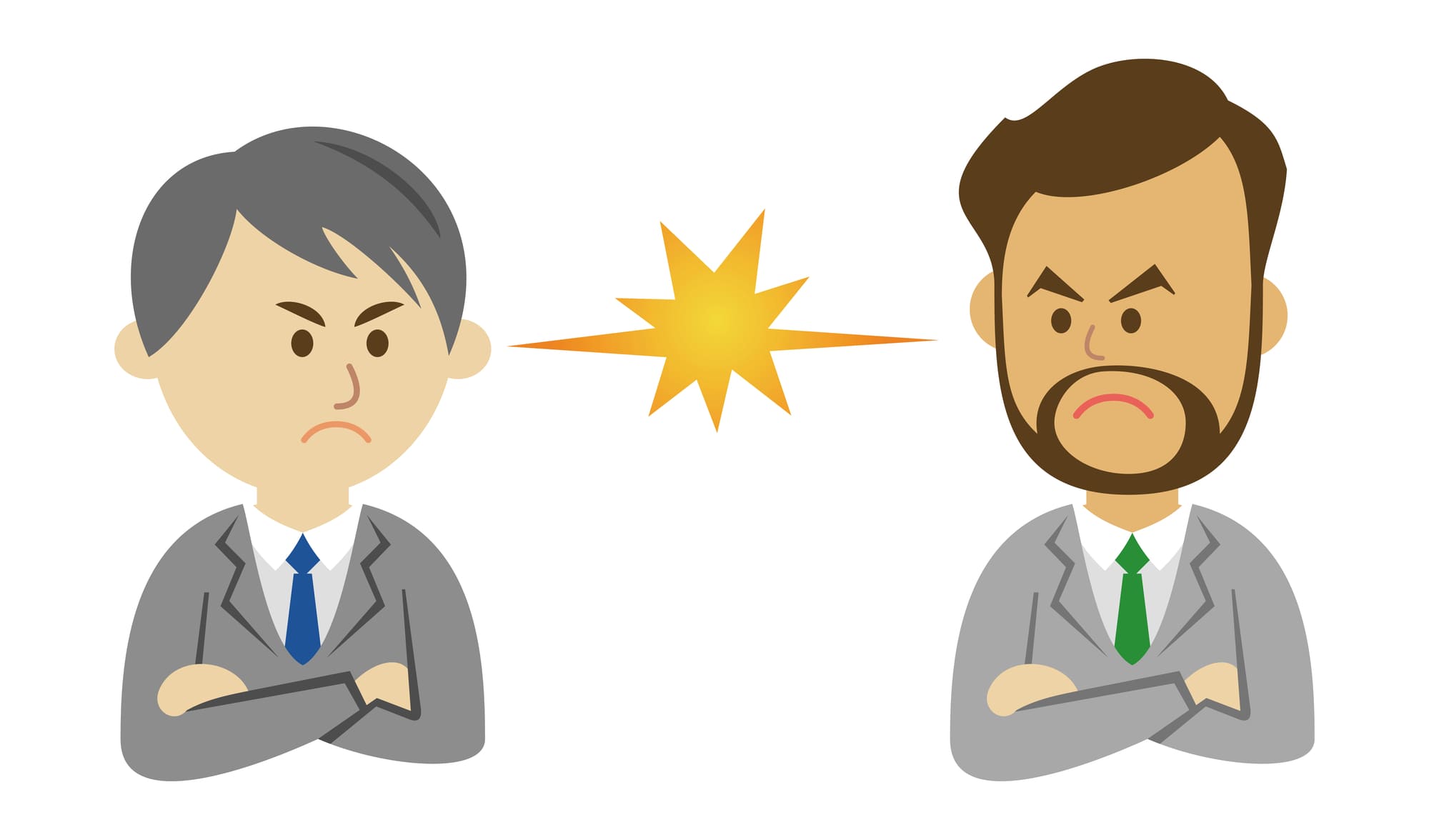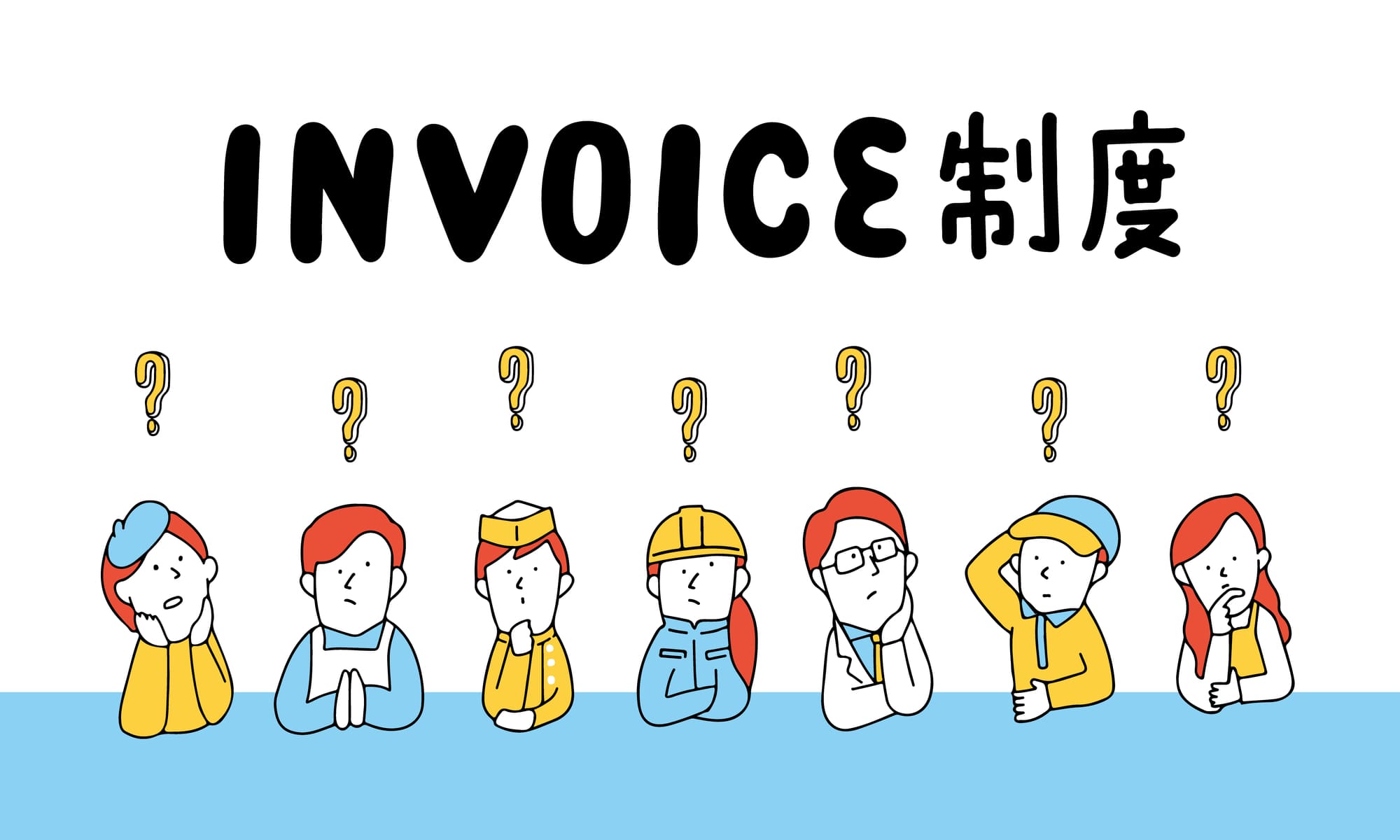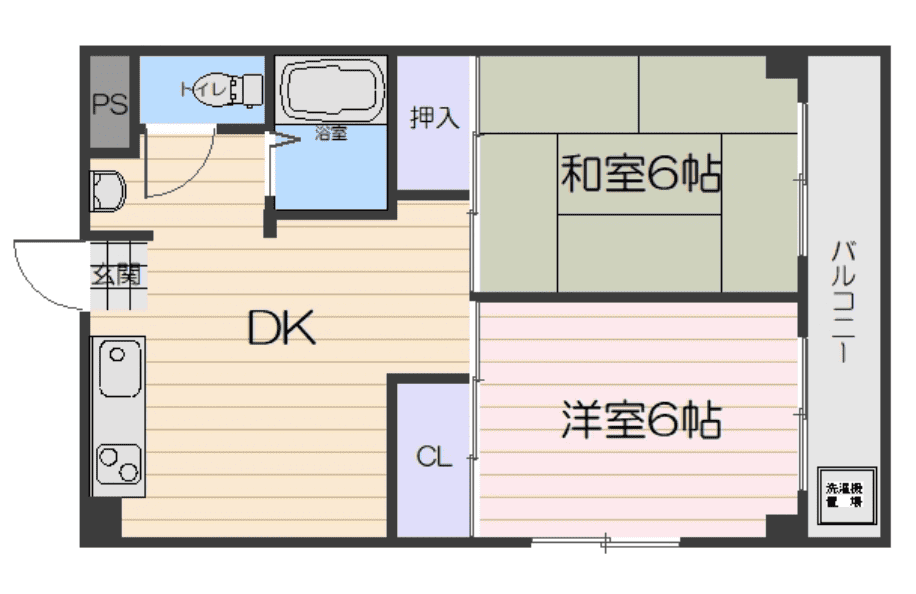制度が新設された理由
例えば、都心部で生活している子供が実家の土地の相続を受けた場合、実家に戻る選択肢がなく処分に困り放置するケースに代表される、都心部への人口移動や、人口の減少、高齢化の進展などが原因となる所有者不明土地の発生を防ぐために新設されたのが「相続土地国庫帰属制度」です。
この制度は所有者不明土地の発生予防を目的としているので、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が利用でき、法務大臣 (窓口は法務局)の承認を受け、国庫に帰属させることで土地を手放すことができる制度となります。
相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば申請が可能で、この制度の開始前に土地を相続したとしても申請できますが、売買等によって任意に土地を取得した場合や法人は対象に含まれません。
また、土地が共有地である場合には、共有者全員で申請する必要があるということに注意が必要です。

どんな土地でも引き受けてもらえるか?
残念ながら、どんな土地でも引き受けてもらえるわけではありません。国に引き受けてもらえる土地かどうかを判断する「却下要件」が設けられています。
「却下要件」には5つあります
1 建物が存在する土地
2 担保権など権利設定されている土地
3 特定有害物質で土壌汚染されている土地
4 通路、その他の人が使用が予定される土地
5 境界が明らかでない土地
まず、この5つに該当する土地は引き受けが却下されます。

また、この「却下要件」が含まれない土地であっても、状況によって引き受け不可の場合もあります。これを「不承認要件」 といいます。
「不承認要件」も5つあります
1 崖がある土地のうち、 通常の管理に必要以上の費用や労力がかかる土地
2 管理や処分を阻害する工作物、車両、樹木、その他の有体物がある土地
3 除去しなければ通常の管理、処分ができない有体物が地下にある土地
4 隣人とのトラブルがあり、争訟によらなければ通常の管理、処分ができない土地
5 通常の管理、処分を行うに際して、過分の費用や労力がかかる土地
法務局が現地調査を行い、この5つのいずれかに抵触した場合、土地を引き受けてもらえないケースがあります。
「却下要件」「不承認要件」ともに、土地の管理や処分を行う際に、費用や労力が過分に必要になる土地は、引き受けられないということです。
必要なコストは20万円強
法務局による現地調査で引き取り可能と判断された場合 、10年分の管理費用が支払われた時点でその土地は国に帰属することになります。
この10年分の管理費用はいくらなのかが気になるところです。これが高額となれば利用しにくく制度として、浸透しないことも考えられます。
10年分の管理費用は、およそ20万円となります。
法務局の現地調査で引き取り可能とされ、20万円を納めれば、その土地の所有権は国に移転します。
この他、申請時に法務局の審査に必要になる手数料が1万5,000円程度なので、土地の大きさによっても違いますが、およそ20万円の管理費用と合わせ、合計21万5,000円ほどが負担金額となります。
なお、法務局への手数料は、現地調査のためのコストとなるので、現地調査後に先の「却下要件」や「不承認要件」に該当し、引き受けが不可と判断されても返金はされません。
まとめ
この制度は、所有者不明土地の発生予防が目的となります。
相続した不動産を処分する際には、売却や相続放棄の方法だけでなく、新たに国庫帰属制度を活用することができます。
制度の活用には、法務大臣の承認が必要となる点に注意が必要ですが、相続する土地の状況によってはこの制度を活用することでメリットが得られる場合もあるので、相続される土地の処分にお悩みの方は、一度制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。