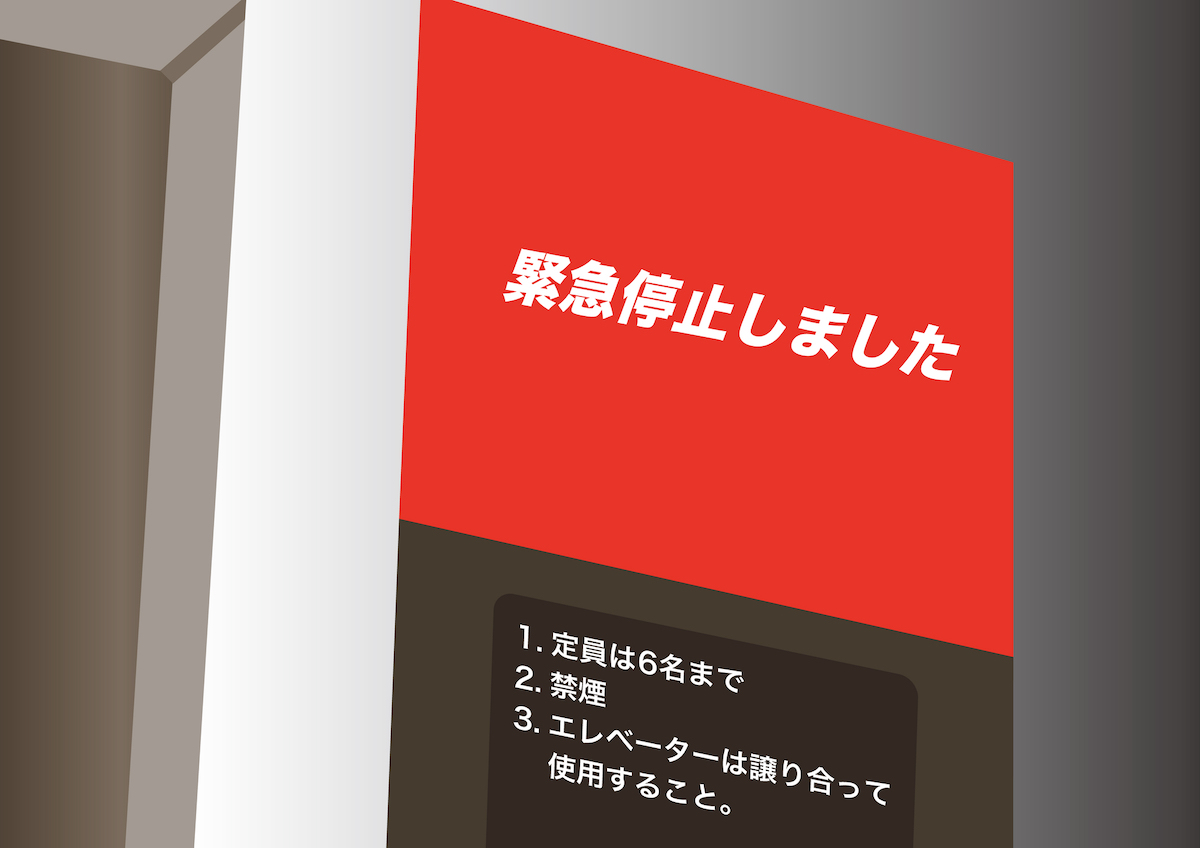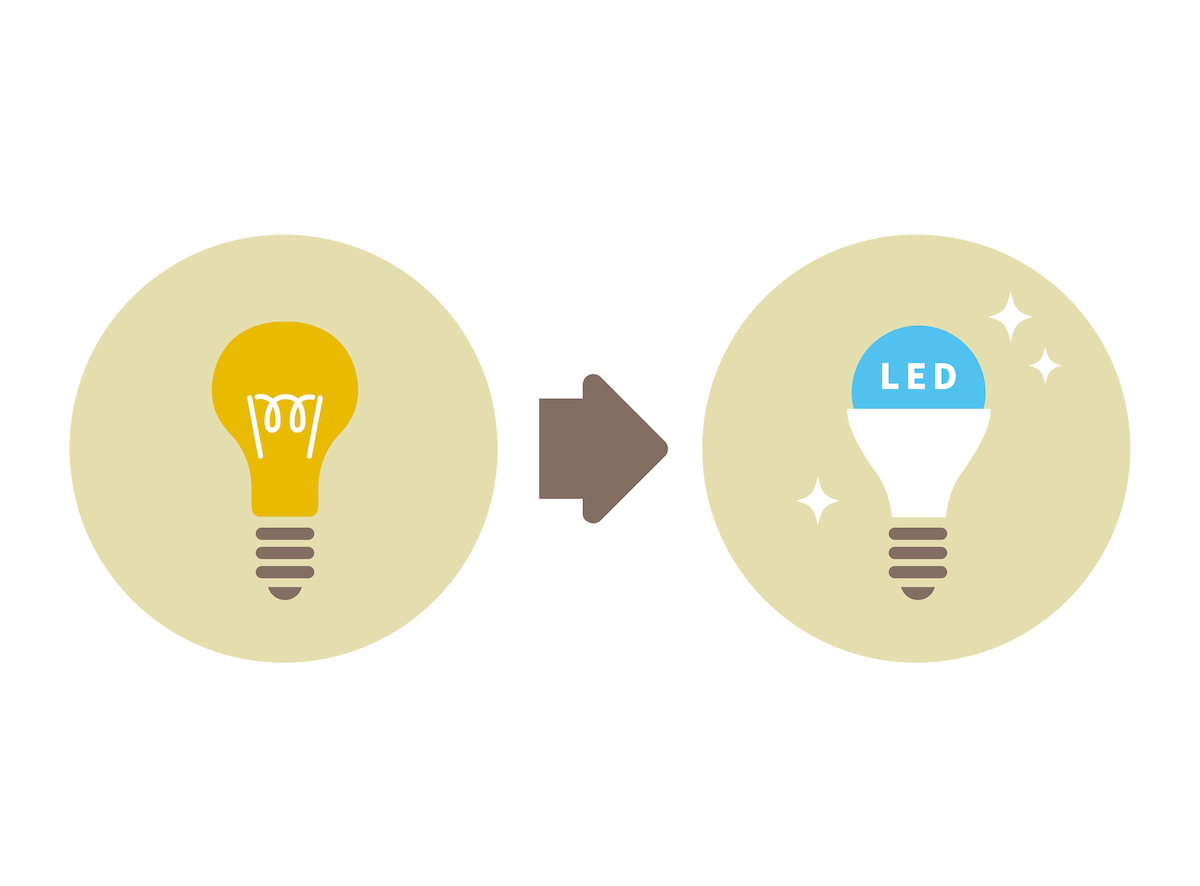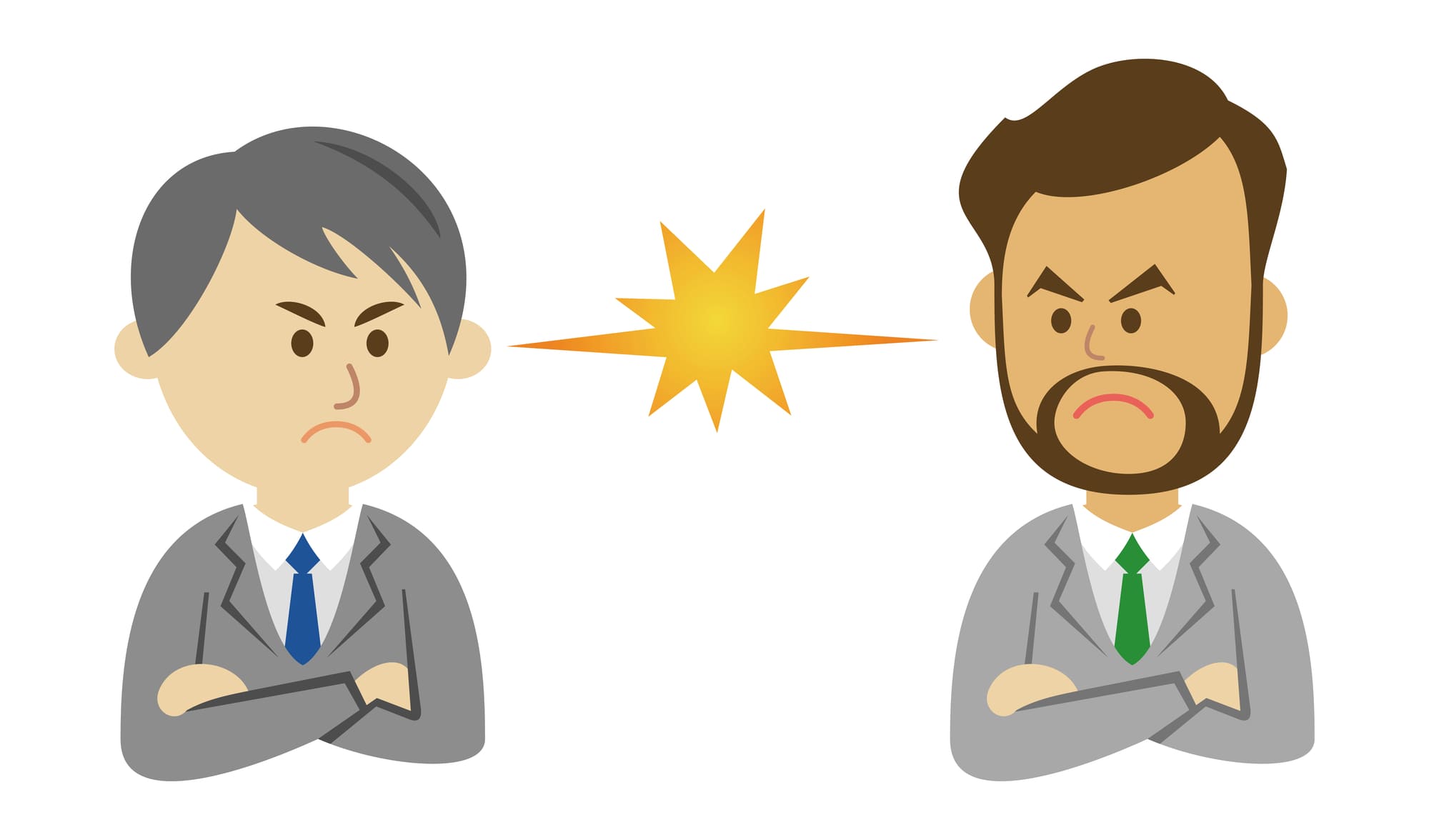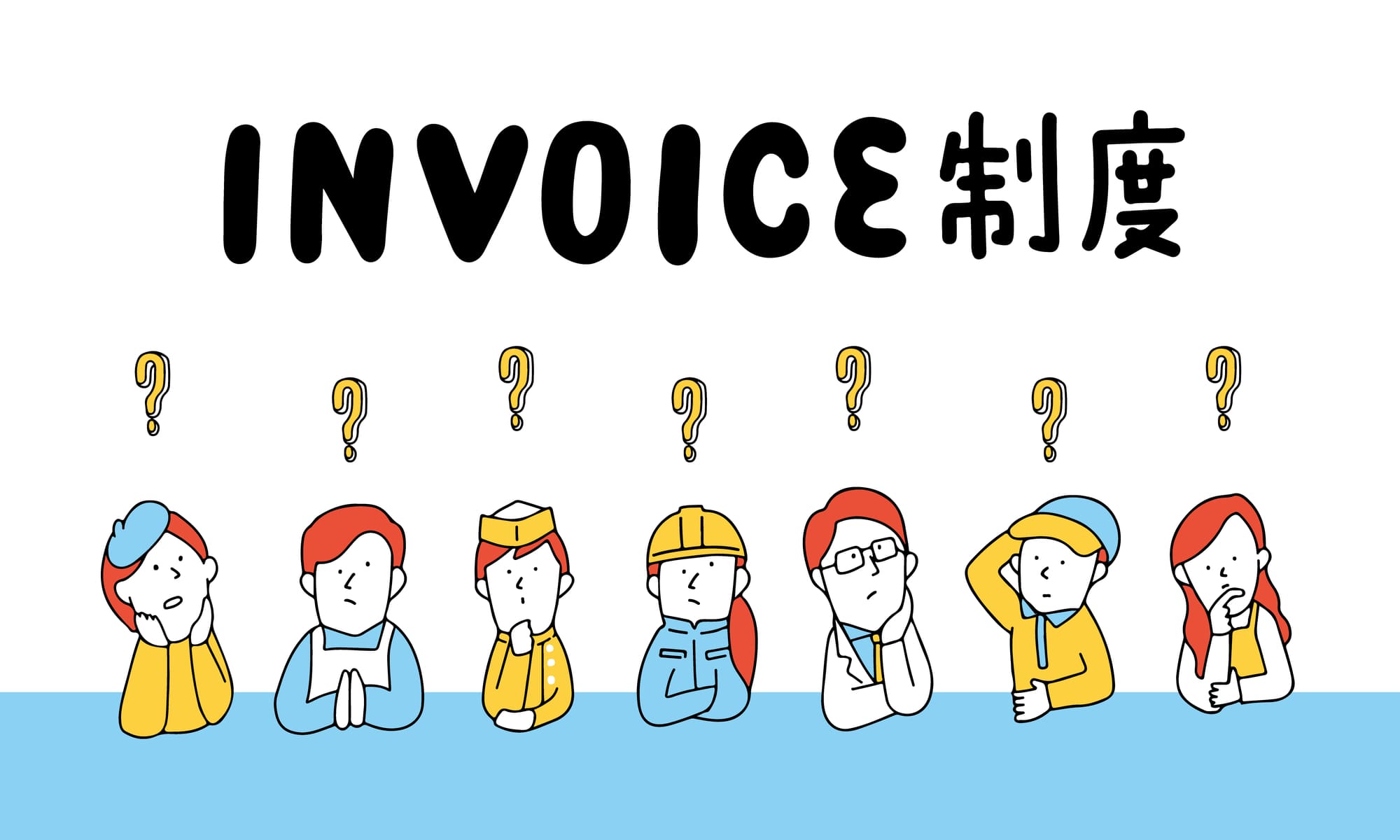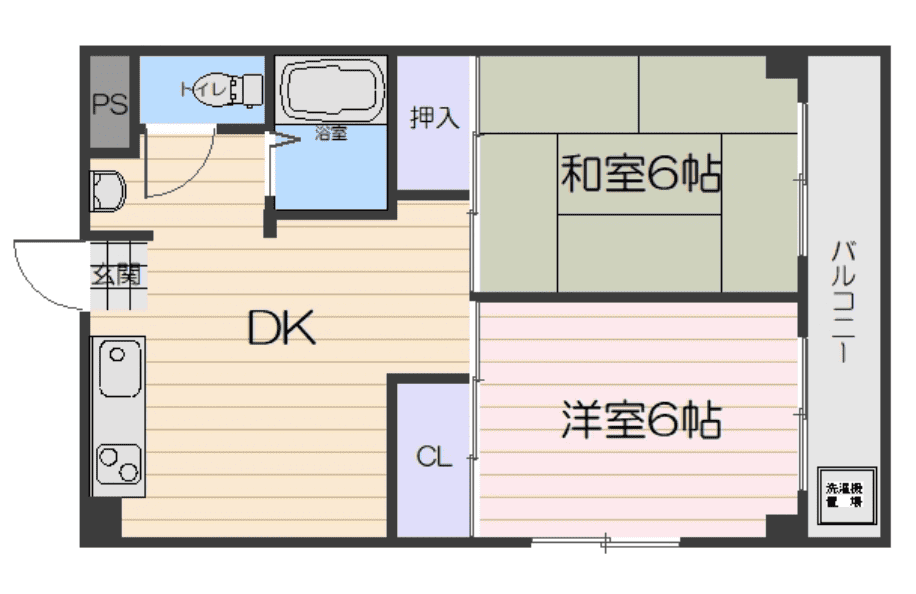現行の民法での対処
隣地の竹木などの枝が越境してきた場合、現行民法では、越境された側が勝手に切除することは許されていません。
切除するには、越境した竹木の所有者が自身で切除してもらう必要があるわけですが、当の隣地所有者が切除を拒否したり、隣地が所有者不明土地の場合には、切除がなされない状況になります。
改正民法でどう変わる?
これは改正民法でも変わりはなく、竹木の所有者に切除してもらう必要があるのですが、次のような場合、越境されている側で竹木の枝を切除することができるようになります。
1. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しなかった。
2. 竹木の所有者を知ることができない、または行方がわからない。
3. 急迫の事情があるとき。
また、隣地の竹木が数人の共有であった場合には、各共有者は、他の共有者の同意等を得ることなく、単独でその枝を切り取ることができることとなりました。共同所有者1人と交渉することができれば、越境した竹木を切り取ってもらうことが可能となります。代々の相続によって所有者が多数になった土地であっても、相続人のうち1人から承諾を得ることができれば、切除できるようになるため管理の立場からすると、有意義な改正だと感じています。

切除した費用はどうなるの?
竹木の切除費用は原則、竹木所有者の負担となります。越境された側がやむなく切除したとしても、竹木の所有者にその費用を請求し負担させることができます。これは隣地に竹木を越境させて不法占拠しているのは、竹木の所有者であるという考えがもとになります。
しかし、実際に所有者側に請求しても支払われない場合や拒否された場合、最終的に裁判などで解決をするしかないことになります。法的な責任の所在と実際に支払われるかどうかは別問題である事に注意が必要です。
切除する際のポイント
この竹木越境による切除問題は、管理をしていると少なくない頻度で発生することから、2023年4月の改正以降、隣地の所有者不明案件などでこうした切除問題が発生した場合には、次の4つのポイントを抑えた対応が管理会社には求められます。
1. 隣地所有者への通知書の作成
2. 弁護士等による「催告文書」のリーガルチェック
3. 費用回収不能時における負担のバランス判断
4. 記録付きの書面にて発送
「3.の負担バランス判断」とは、やむなく越境している竹木を切除した場合、万一にその切除費用が回収できないことを想定して考えることになります。
その費用の金額負担と、越境が与える影響の負担、迷惑の度合いとを比較して、切除すべきかどうかの判断をすることです。越境が与える影響が小さい時は催告はしても、切除まではしないほうが賢明です。
特に、「2. 催告文書のチェック」 が重要ポイントです。
「相当の期間の設定」と「急迫の事情」について、わかりやすく記載する必要があります。
具体的には、次の3点の記載が必要です。
・「なぜ切除してほしいのか。」の理由
・「切除をしないとどのような被害・影響が予測できるか。」
・「〇月〇日までに回答なき場合は・・・」等の期限の設定
この催告文書は、後々の費用請求等の紛争となった場合のことを想定しているので、弁護士などのチェックを受けることが必要だと思います。

今回の改正によって隣地の迷惑な竹木は切除がしやすくなるとはいうものの、きちんと手続きを踏まず強引に進めてしまうと、費用の請求を拒まれることだけでなく「権利の濫用」とみなされ、違法と判断されてしまうこともあり得ます。
今後、管理上で発生する対応時には、こうしたリスクを理解し、先の対応ポイントをきちんと踏まえた上でリスク回避の対応が必要になると考えています。
隣地の越境する竹木にお困りの際には、参考にしていただき、不明点等のご相談もお受けしていますので当社までお声がけください。