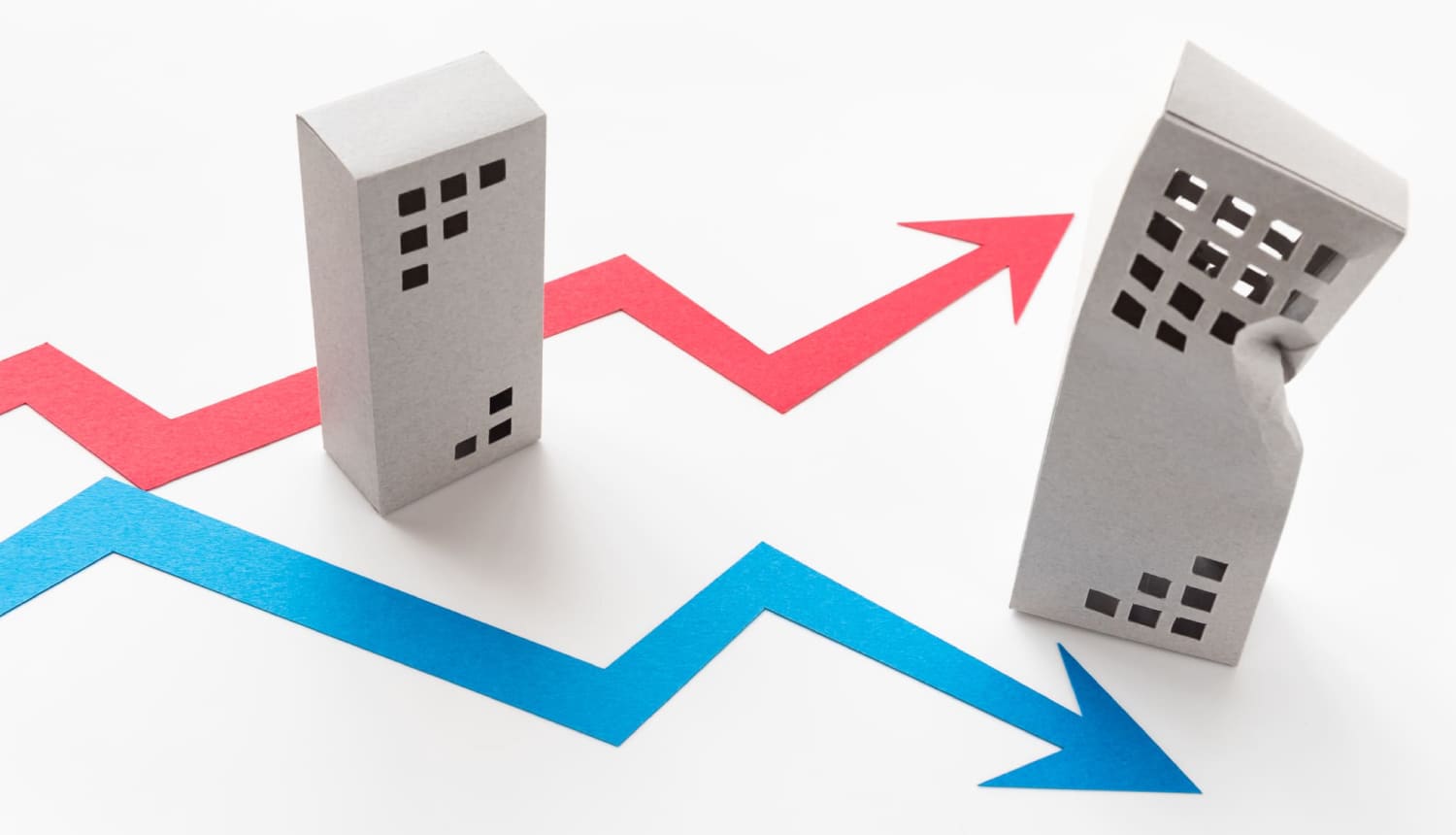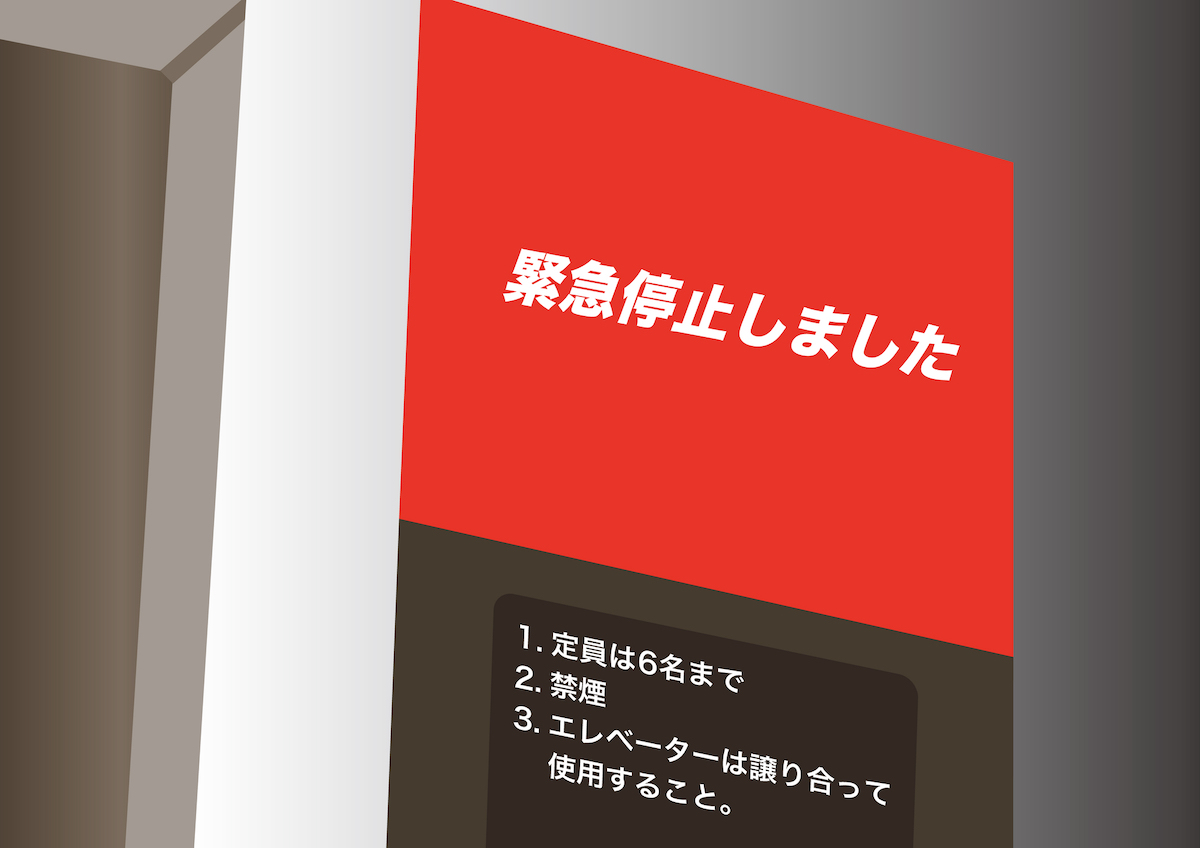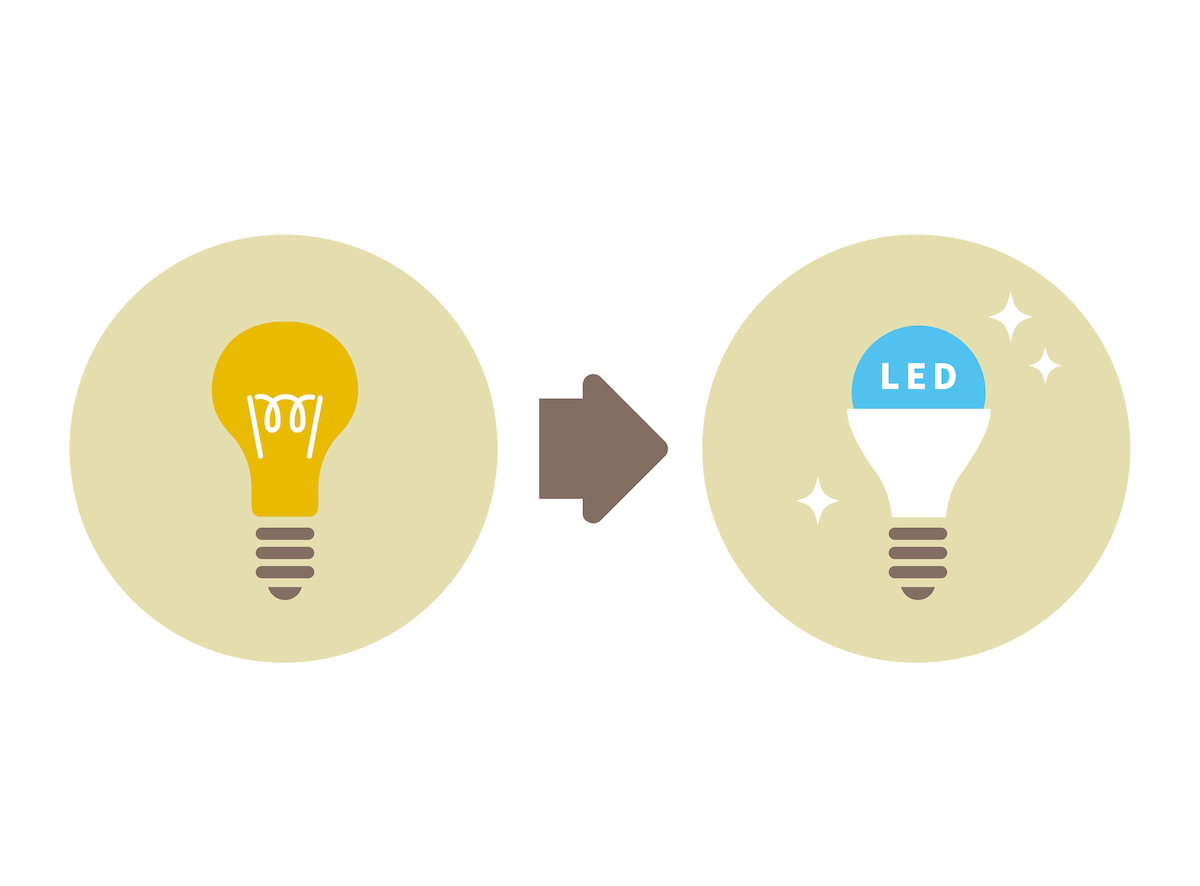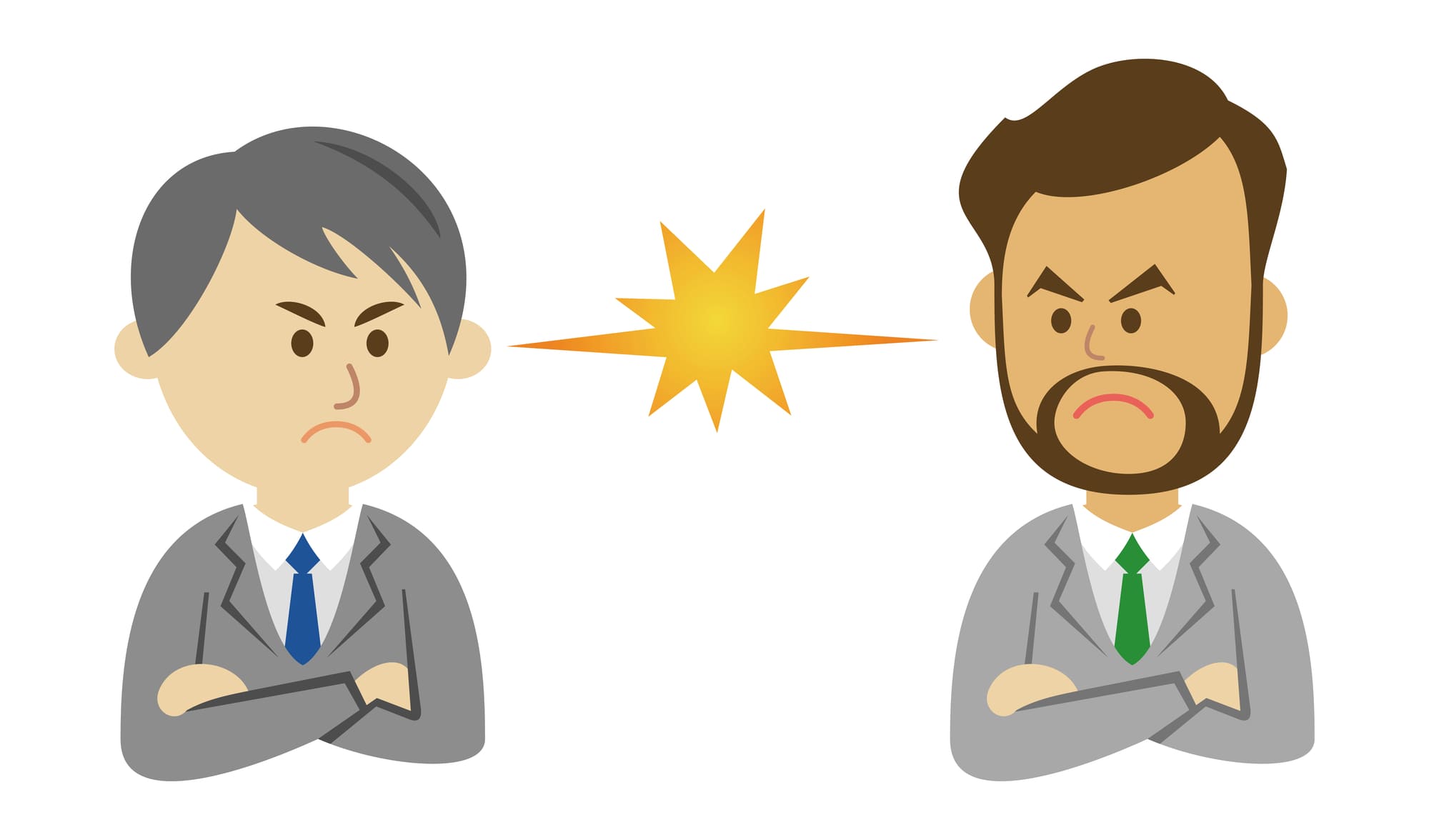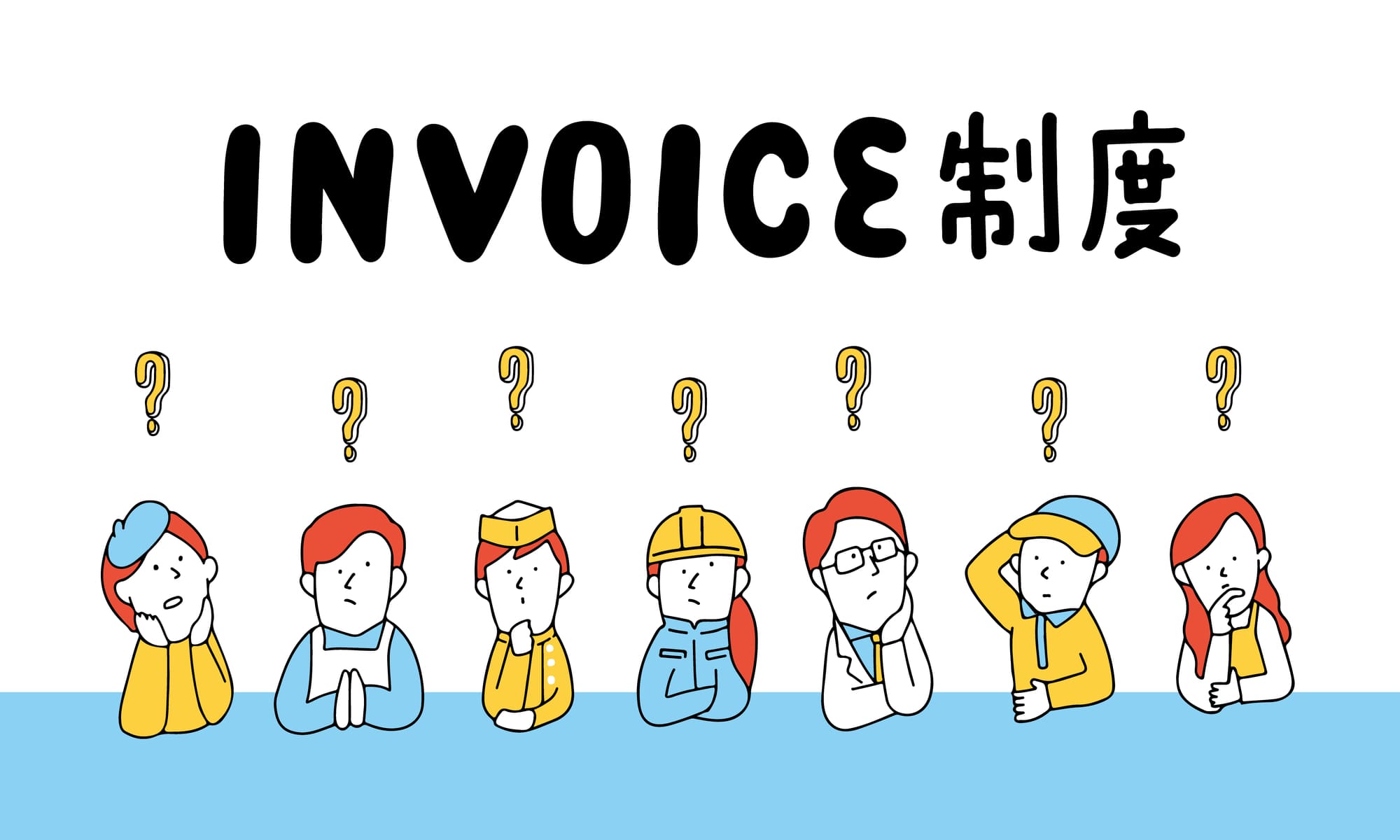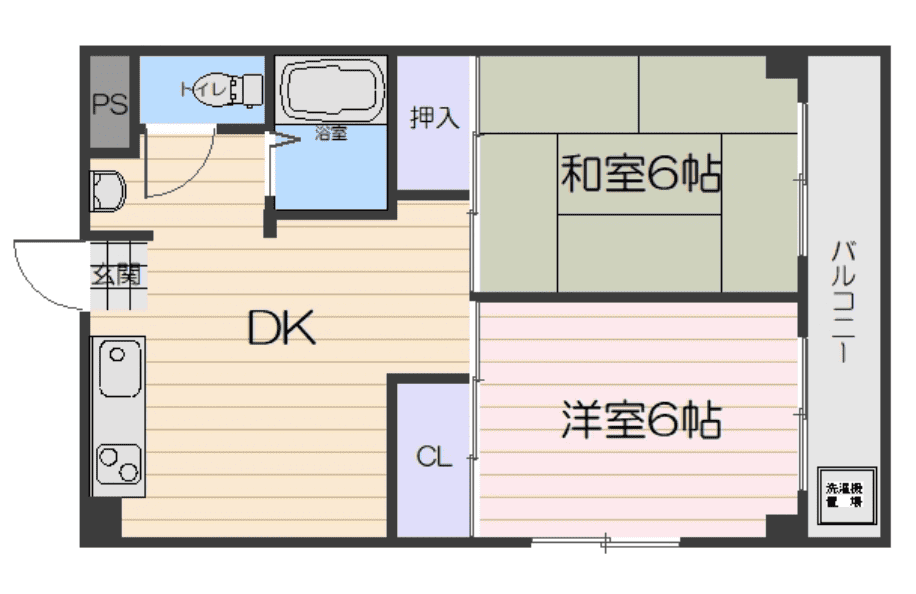事故物件のガイドラインが策定
国土交通省が、過去に死亡事故が発生した不動産について、不動産業者が売買・賃貸の契約者となる買主や借主に告知すべき対象などをまとめた「ガイドライン案」を策定。
2021年10月「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」として発表しました。
なぜガイドラインが策定されたのか?
人の死は日々発生していますが、それが心理的瑕疵に該当するかどうかや、いつまでその影響をうけるかなど明確な基準がなく、これまで各事案によって判断するとされてきました。
その為、人の死に関わる事案はどんなものでも告知する義務があるとした誤解も生まれてしまい、特に高齢者入居の妨げになっているという指摘があります。
こうした問題から、不動産取引において過去に人の死が発生した物件を取り扱う場合に妥当であると判断できるガイドラインが策定されました。
誰に対するガイドラインなの?
このガイドラインは、宅地建物取引業者に向けたものになります。
取引きされる不動産で過去に人の死が生じていた場合、トラブルの未然防止の観点から、現時点においての裁判例や取引実務に照らし、妥当と考えられるものを整理しとりまとめたものが今回のガイドラインとなります。
ガイドラインが対象とする不動産
今回のガイドラインが対象としたのは「居住用不動産」
居住用不動産は、人が継続的に生活する場であり、買主や借主は、快適性、住み心地の良さなどを期待して購入または賃貸し入居すると考えられるので心理的な影響が大きいことから居住用不動産を対象とされています。
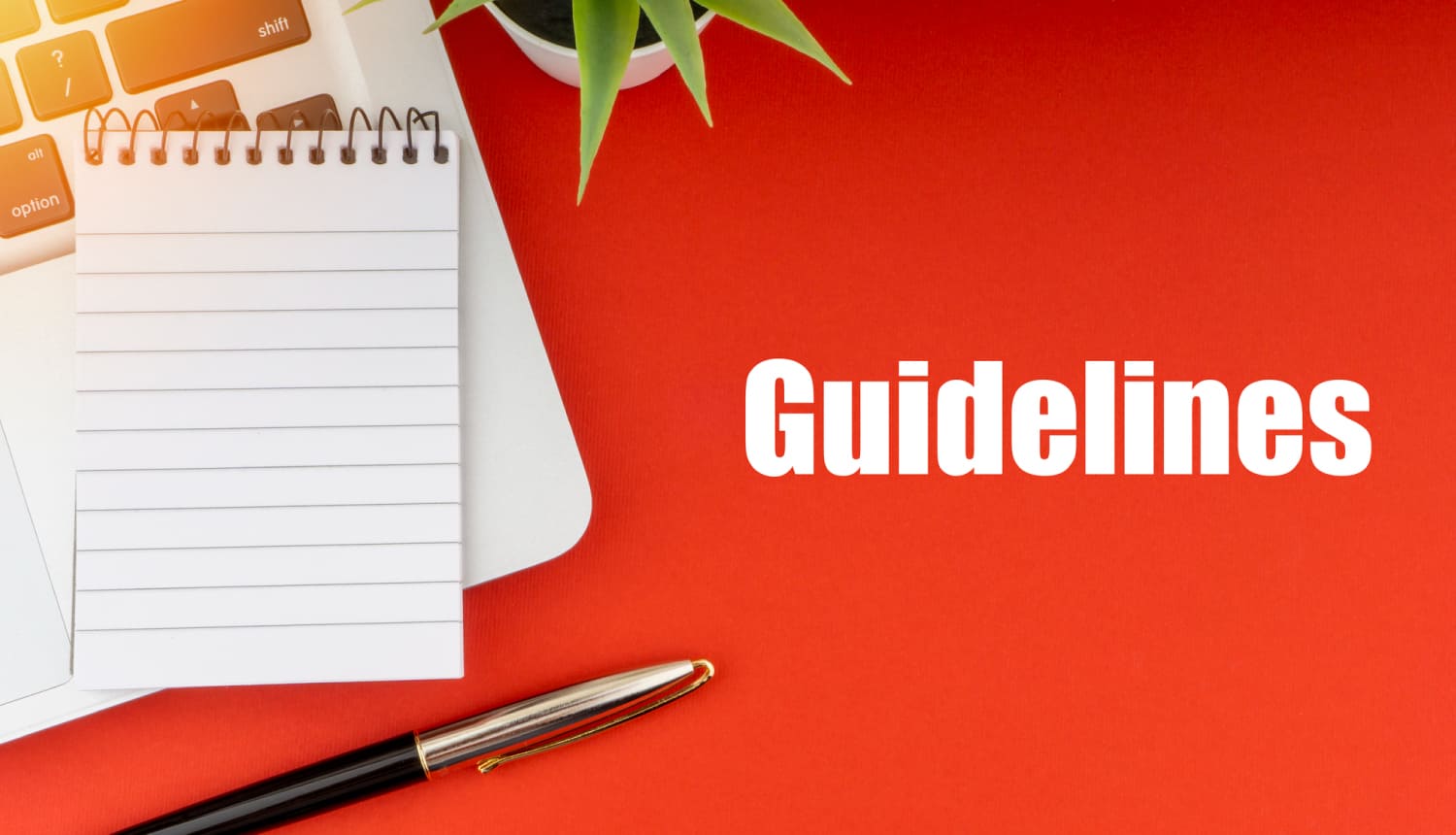
ガイドラインの3つのポイント
ポイント①
自然死又は日常生活の中での不慮の死が発生した場合は告知不要となります。
「自然死」とは、老衰や持病による病死などのことを言い、「日常生活での不慮の死」とは、自宅の階段からの転落、入浴中の溺死や転倒事故、もちをのどに詰まらせたことで亡くなった場合など、そうした死が生ずることが当然に予想されるもののことを指します。このような場合は告知をする必要はありません。
しかし、死因がこうした場合でも、長期間放置されたことで、特殊清掃や大規模なリフォーム等が行われた場合は告知が必要であるとしています。
ポイント②
賃貸の場合のみ、告知が必要となった死が発覚して概ね3年以上経過した場合、告知不要となります。
ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響が高い事案の場合はこの限りではありません。
注意すべきは賃貸の取引のみの規定であるということです。
ポイント③
買主や借主から過去に人の死があったかどうかを聞かれた場合や、社会的影響や心理的瑕疵の程度が大きい事件の場合は、上記ポイント①②に関わらず告知が必要となります。
告知内容とその方法
氏名・年齢・住所・家族構成や具体的な死の態様、発見状況まで告げる必要はありません。個人情報の観点から、告知を行う場合、亡くなった方やその遺族の名誉及び生活の平穏に十分に配慮し、これらを不当に侵害することのないようにする必要があります。
またその告知方法は、後日のトラブル防止の観点から、書面の交付等による告知が望ましいとされています。
まとめ
このガイドラインに法的拘束力などの強い力がある訳ではありません。告知義務違反で損害賠償等訴えられた場合、今までの裁判判例や事案の具体的内容などから判断されることになります。
しかし、国が定めた心理的瑕疵のガイドラインであるとして、事案発生やトラブルになった際にはこのガイドラインが判断材料として考慮されることが考えられます。またガイドラインが整備されたことで、契約後のトラブルの未然防止になるという期待も含まれています。
これまでは、告知の基準、範囲やその期間など不透明であったため、若年層と比べると、病死や孤独死のリスクが高い高齢者の受け入れハードルは高いものでした。
今回のガイドライン策定によって、病死や孤独死については取引時に原則、告知不要と判断され、高齢者の入居促進につながることが期待されています。
今サービスが拡充し続けている高齢者の見守りサービスなどをうまく利用することで、高齢者の受入れに積極的な物件も増えるてくると考えられます。
ガイドライン策定を機会に「見守りサービス」の導入などを通して、入居者ターゲットの拡大を検討しようと考えられる場合は、是非当社にご相談ください。